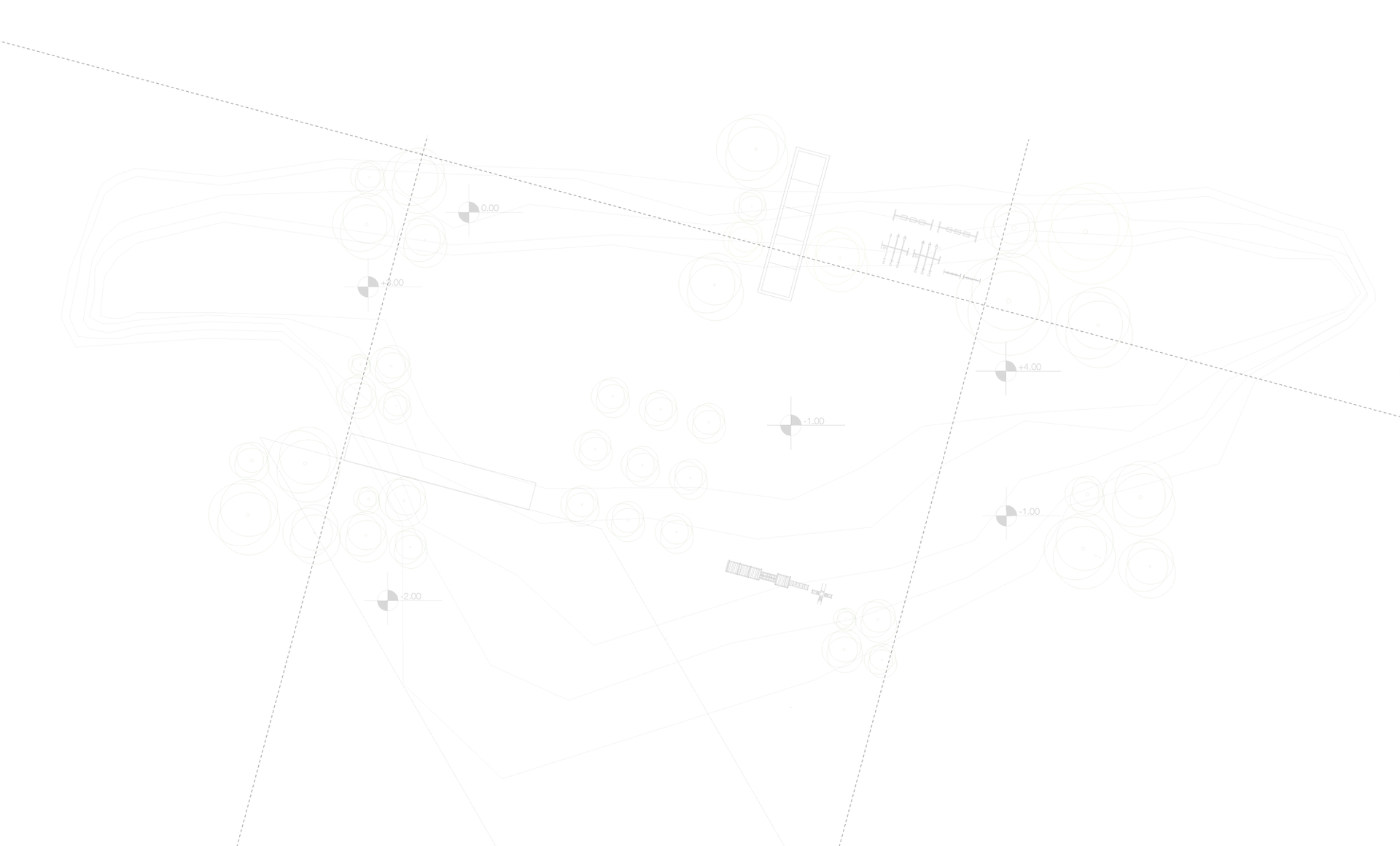
カランと来客を伝える音が隼人の耳に届く。入口に視線を向けると、入店した人物は既にお目当ての席へと向かっていた。お目当ての席──伊折達の席に座っていた劉燐が、真っ先にその人物に気が付き、しまったというよなうな、焦った表情を見せた。そんな彼女の様子に、一緒に座っていた三人も気が付き振り返る。それと同時に、来客者がテーブルに思い切り手をついた。グラスが少しだけ揺れる。
「劉燐……お前さあ……」
「や、やあ劉院。お母さんの具合はどう?」
「分かってんだろ。元気だったよ!」
「……怒ったよね、ごめん」
怒られる覚悟も、嫌われる覚悟もしていた。しかし、予想以上に早い本人の登場に少しばかり焦燥感を覚える。本当は、これ以上彼に嫌われるのが怖いのかもしれない。そんな気持ちを誤魔化すために、劉燐は無理やり笑顔を繕った。いつもどおり、へらへらしておけばいい。そうすれば、少しだけ気が楽になる。彼の気持ちを踏みにじったのは、自分なのだから仕方の無い事だ。
「怒ってる。でも、別に嘘をつかれたから怒ってるんじゃねえよ」
劉院が大きくため息をついた。
「……もういい」
「……!」
「もういいから。俺のために何かを犠牲にするのはやめてくれ」
「そんなつもりは……」
「学院に入学したの、俺のためなんだろ」
「……あんた、昨日そこまで聞いてたの?」
先程、伊折達に打ち明けたとは言え、そこまで彼が知っているとは思っていなかった。思わず、三人にどうして教えてくれなかったのかと視線を送る。しかし、三人揃って知らんぷりをするものだから、やられたもんだと苦笑を浮かべた。
「さっきの嘘だって、俺のためだ。全部分かってる」
「……劉院、お母さんと仲直りできた?」
「ああ。もう、十分だ」
「そっか……良かった……」
「なあ、あんた本当は学院に入学するよりもやりたいことがあったんだろ」
彼女が昔から海外に憧れを抱いていることを知っていた。いつか、旅をしてみたいと目を輝かせながら、そう言っていたのはいつの頃だったろうか。そして、そんな夢の話をしなくなったのは、いつ頃だろう。劉院は、自分のことで手一杯で、彼女の変化に何も気がつかなかったことを酷く後悔していた。
「それは、いいの……」
「……心配かけたことは謝る。悪かった。でも、もう大丈夫だから、あんたも──」
「討伐団員になることを諦めるつもりはないんでしょ?」
「それは……そうだけど」
「じゃあ、大丈夫なんて簡単に言わないで!この先、何が起こるかも分からないのに……!」
大きな声が響き渡り、店内が静まり返る。
劉燐は両膝の上で拳を握った。声が少しだけ震えている。
──心配するくらいなら、信じてほしい。
伊折の言葉が頭の中で反響した。
信じたい気持ちはもちろんある。しかし、どれだけ大丈夫だと言われても、どれだけ信じることが出来たとしても、彼のことを心配する気持ちは揺るがない。それだけ、彼女にとって劉院は大切な家族だった。例え、彼が己のことを家族だと思っていなかったとしてもだ。
「……分かった」
「あ……」
長い沈黙を破ったのは劉院だった。その声が、悲しみを含んでいるのが分かる。
(ああ、またやっちゃったな……ごめん、劉院。私、あんたにそんな顔させたいわけじゃないのに)
彼とこうして喧嘩をするのは何度目だろうか。数え切れないほどこうして口論を繰り返してきた。その度に、彼は酷く悲しい顔をするのだ。それが、いつも心苦しかった。
「じゃあ、心配いらなくなるまでは、あんたも好きにしたらいい」
「……え?」
思いがけない劉院の言葉に、目を見開いた。いつもならば、ここで彼は適当な言い訳を並べて立ち去っているはずだった。しかし、今日は違った。少しだけ悲しそうな顔をしながらも、しっかりと彼女を見据えていた。
「あんたが俺のこと心配だっていうなら満足するまで学院にいたらいい」
「満足したら?」
「その時は、あんたも自分のために好きなことをするって約束してくれ」
「……私の好きなこと」
彼の言うとおり、海外への憧れが既に全く消え失せているとは言いきれなかった。親が海外を飛び回っているというチームメイトの話を聞けば聞くほど、憧れていた日々を思い出すようになったくらいには、まだ彼女の心にその夢は残っている。
「強くなって、いつか絶対、もう心配いらないって言わせてやる。……心配させないよう、努力もする」
「具体的には?」
「実家に帰る」
「……本気?」
「さっき、母さんとも話した。本気だよ」
劉燐の心配だけを拭い去っても意味がないことを劉院はよく理解していた。叔父や親戚、今まで心配をかけてきたたくさんの人に納得してもらう必要がある。ようやく、向き合う覚悟ができた。
「なあ、ここまで言ってんだ。今すぐは無理でも、これから先、あんた達もこいつを信じる努力をしてやってくれよ」
「……」
静かに二人のことを見守っていた伊折が、もう一度劉燐に語りかける。今すぐは無理でも、きっといつか、信じて貰える日が来る。そう、確信していた。
「……分かった。私の負け」
「!」
伊折の言葉に後押しされ、少し考えこんだ劉燐は困ったように笑いながら両手を胸の前に掲げた。緊張の面持ちで傍聴していた姫と林檎が視線を絡ませてから手を取りあう。劉院も、いつもは逃げてしまう場面だっただけに、ようやく向き合えたことにほっと胸をなでおろした。
「……劉院が前を向こうとしているなら、それを応援する。お父さんにも、私から話をしておくわ」
「劉燐、いつもありがとう。それから……我儘ばっかり言ってごめん」
「いいのよ、気にしないで。家族だもの、それくらいの我儘、当たり前のことよ」
「……うん」
「さてと、じゃあ、私はそろそろ行くわ。隼人さん、騒いでしまってごめんなさい。コーヒー美味しかったわ」
席を立ち、カウンターで代金を支払いながら申し訳なさそうに頭を下げる。そんな劉燐に、隼人は「また来てな」とだけ言って笑った。
ツバメの巣を後にしようと、扉に手をかけてから、不意に彼女はもう一度劉院達の方を振り返った。劉燐が座っていた場所に、劉院が座っている。彼のあんなに明るい表情を見たのはいつぶりだろうか。
(……劉院のチームメイトが、あの子達で良かった。これからも、よろしくね)
心の中でそっと願いながら、今度こそ店を後にする。持ってきていた傘を広げようと手にかけるが、雨が止んでいることに気がついて顔を上げた。
空には、雨上がりの虹がかかっている。今年は少しだけ早い梅雨明けが期待できそうだ。
