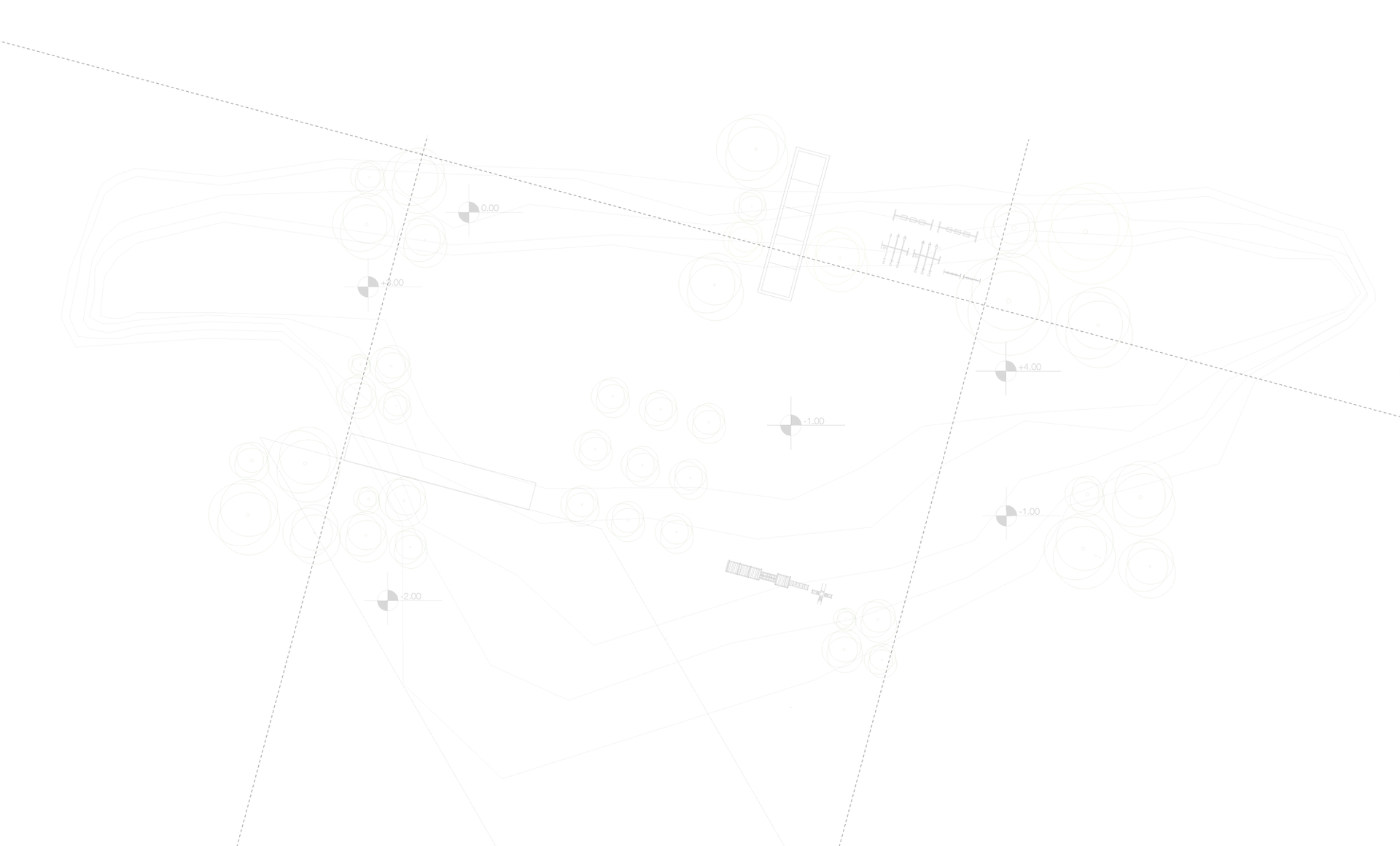
公園のベンチに座って、小さなこども達が遊んでいるのをぼんやりと眺めていた。この景色を夢で見るのは何度目だろう。無意識に父の姿を探した。
「劉院」
父は、すべり台に続く階段の前に立っていた。いつもと変わらない優しい笑顔を向けて、こちらに手を振っている。
「父さん」
「頑張ったね」
「……!」
父の言葉に、瞼が熱くなる。ずっと欲しかった言葉だ。心配されるよりも、気を遣われるよりも、ただ頑張りを認めてもらいたかった。それだけだった。
「たくさん苦労させてごめんな」
「……ううん。俺こそ、ごめん」
「はは、そんな顔するなよ」
声を震わせて頷く劉院を父が抱きしめる。頭を優しく撫でてから、更にもう一度強く抱きしめた。父のぬくもりを感じながら、これで最後なのだと劉院は悟った。
「もう行くね」
「……うん」
「母さんのこと、頼んだよ」
「……任せてよ」
力強く頷けば、父は満足気に笑った。そして、すべり台へ続く階段をひとりで登っていく。劉院は、その後ろ姿を静かに見送った。ふと、父が最後にこちらを振り返った。
「ああ、そうだ。言い忘れてた。劉院──」
残念ながら、父の最後の言葉を聞き終える前に目が覚めた。先に起きていたらしい母が、部屋の入口でちょうど顔を覗かせているのが目に入る。
「起きたのね。おはよう」
「……母さん、おはよう」
少しだけぼんやりとした頭を覚醒させながら身体を起こせば、歩み寄った母が額に手を当てて心配そうに顔を覗き込む。
「具合はどう?まだ熱があるかしら」
「ん……大丈夫。多分、もう熱は下がったよ」
「そう?なら良かったわ」
家出から一週間が経っていた。
雨にうたれたこともあり、熱をぶり返したのは一昨日のことだ。
「明日は登校できそうね」
「うん……母さんは具合悪くない?」
「しばらく調子が良いわ」
「調子にのるとすぐ悪くなるよ」
「ふふ、手厳しいことを言うじゃない。でも、そのとおりね。あまり無理はせず大人しくしておくわ」
そう言って、盆にのせて持ってきていた水をカップに注ぐ。劉院に手渡してから、ふいに母がそうだ!と手を叩いた。
「兄さんから預かってるものがあるの」
「?」
渡された水を喉に通しながら、部屋を出て行く母に首をかしげる。数分後、部屋に戻ってきた母は小さな紙袋を持っていた。
「劉院、今日が何の日か分かる?」
母が嬉しそうに笑う。カレンダーに視線を向けると、赤いペンで日付が丸く囲まれていた。
「劉院、お誕生日おめでとう」
十六歳の誕生日を迎えたのだと気がついたのは、母にそれを渡されたとき。中身が赤い宝石の嵌められた数珠であることに気が付き、思わず顔を上げた。
「これ」
「……兄さんとお母さんと、それから劉燐ちゃんから」
叔父達と腹を割って話をしたのは熱をぶり返す数日前のことだった。叔父達は今までのことに頭を下げた劉院に驚いた様子だったが、同時に安堵の表情を浮かべていた。劉院自身も、彼らの本音を聞き、叔父達の気遣いや心配が、彼らなりの愛だったのだとようやく受け止めることができた。
「本当は兄さんから渡して貰えたら良かったんだけどね。今更照れてるのよ」
「ありがとう……大事にする」
増幅アクセサリーであるそれは、叔父が討伐団員になるために学院に残ることを認めてくれた証だった。それがなによりも嬉しくて、大事に両手で握りしめる。
「それから、携帯がたくさん鳴っていたわ」
母の言葉に少し驚きながら、携帯を確認すると、確かにたくさんのメッセージが届いてるのが目に入る。日付が変わってすぐに送られたものもあれば、つい先程届いたらしいメッセージもあった。どれも、お祝いの言葉が綴られている。
「たくさん友達ができたのね」
母はまるで自分のことのように嬉しそうに笑った。劉院はというと、たくさんの人が自身の誕生日を知っていることに驚いていた。
親友である航琉や一部の友人に聞かれた際になんとなく答えた記憶はあるが、ここまでたくさんの人に教えた覚えはない。たまたま誰かが話題にした結果、少しずつ広まっていったのだろうか。
どんな理由があれど、誕生日を最近知ったらしい友人達からのメッセージが届くのは、これまで劉院が築き上げてきた友好関係があるからこそだ。いつの間にか、たくさんの友人や仲間に恵まれていたのだと改めて実感し、嬉しい半面、なんだか照れくさくも感じた。明日はどんな顔をして登校したらいいのだろうかと思案する。その時、携帯がチャットアプリに新たなメーッセージの受信を知らせた。
『おはよう。体調はどうだ?』
『誕生日おめでとう!』
『明日は登校できそうか?佐折兄ちゃんがクッキー焼いてるんだ。持って行くから、食べてくれ』
伊折からのメーッセージに添付された写真には、色々な形を型どったクッキーの生地が並べられていた。曰く、劉院が誕生日であることを何気なく話したところ、料理好きの兄が張り切って作り出したという。彼の二番目の兄と顔を合わせたのは家出をした日の一度きりだが、なんとくなく彼らしいなと思った。
「あら、可愛いクッキー!明日は絶対に登校しないとね」
「……そうだな」
思わず笑みがこぼれる。照れくさい気持ちは残るが、祝福してくれた友人達にしっかり礼を伝えなければ。まずは、明日のために体調を万全に整えよう。
「今日はお母さんに全部任せて、劉院はゆっくりしてなさい」
「うん、ありがとう。でも、無理はしないでくれよ」
「後で劉燐ちゃんが様子見がてらケーキを買ってきてくれるって言ってたから、何かあっても大丈夫よ」
そう言って、母は劉院の部屋を後にした。ひとりきりになった自室で、もう一度携帯のチャットアプリを開く。届いたものから順番に返信を打ち込んでいると、ふいに生暖かい風が吹き込み劉院の頬を撫でた。
揺れるカーテンを開けて、窓の外を見上げると、澄んだ青空が広がっている。梅雨明けにはもう少しかかるようだが、晴れ間の広がる日も増えてきていた。
──劉院、お誕生日おめでとう
夏の風に紛れて、夢の中で聞きそびれた父の声が聞こえた気がした。
(父さん……俺、また頑張るよ。今度は失敗しない。ひとりじゃないから……心配いらないよ)
心の中で父に語りかけると、もう一度風が吹く。父が隣にいるような気がして、ふと顔を上げるがそこに父の姿はなかった。代わりに、視線の先、窓際に飾られた写真立ての中では、父と母が幼い劉院を抱きしめて笑顔を浮かべていた。
…fin
