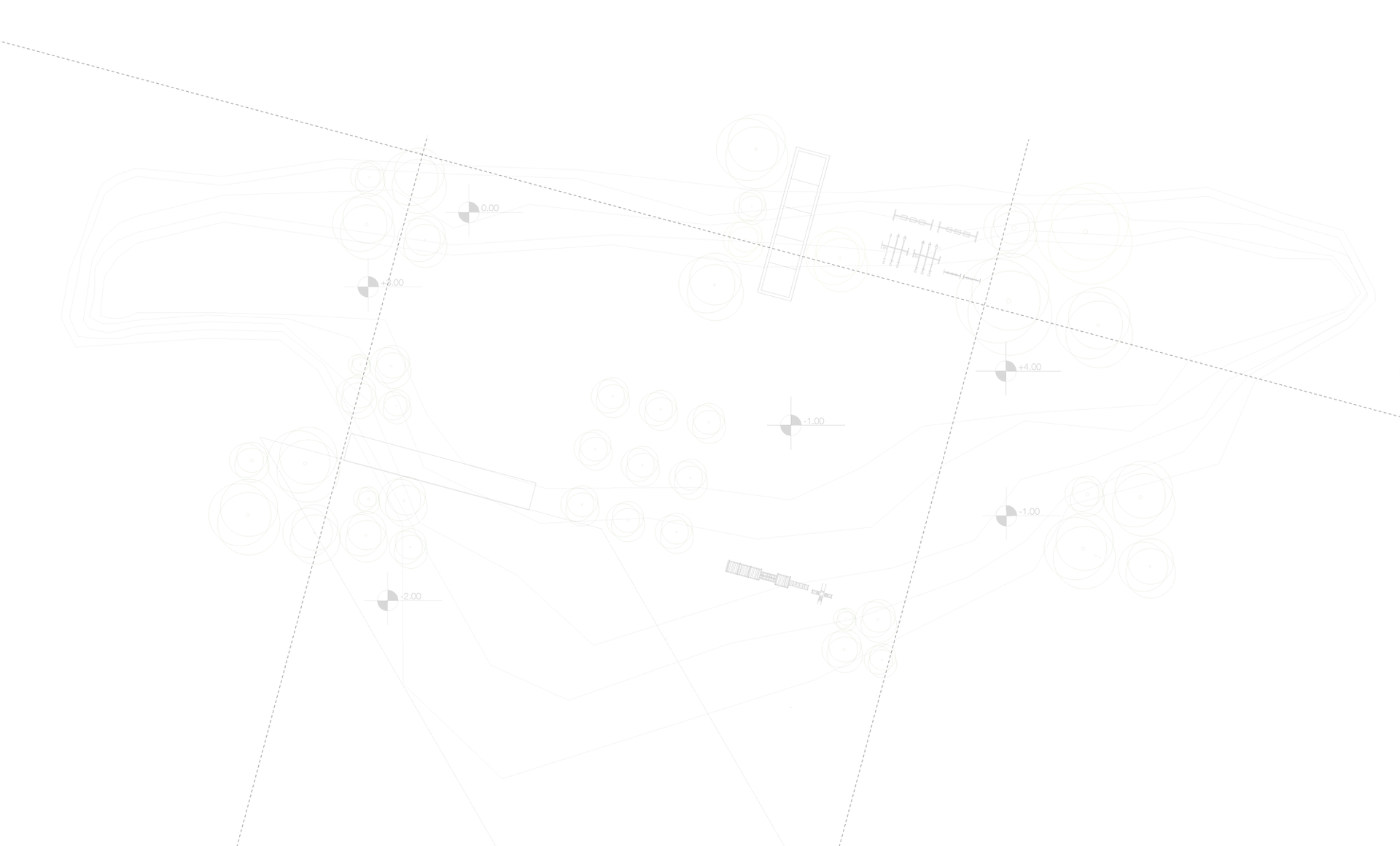
授業を終えた学生達が街に繰り出すには少し早い時間。伊折はチームメイトと共にツバメの巣のボックス席に座り、小雨の降り続く外の様子をぼんやりと眺めていた。隣では、姫が不安そうな面持ちで手を握っている。
「劉院くん大丈夫かな」
「一緒について行ってやりたかったけど、大勢で押しかけるとお母さんの身体に障るだろうし……今は待つしかねえよ」
「心配しなくても、きっと大丈夫よ」
母が倒れたという知らせを聞いた劉院は、ひとりで家に帰ると決めたため、三人は午後からの対抗戦を棄権し、ツバメの巣へと赴いた。なにかあればすぐに自分達を頼れるようにと、劉院にもそう伝えてある。
店のオーナーである隼人も、いつもより少し早い来店に驚きはしたものの、昨日のこともあり特に咎めることもなく三人を迎え入れた。
隼人がまだ客足の少ない店内で、のんびりと珈琲豆を焙煎していると、不意にカランと店のドアが開く音がする。伊折は、そろそろ学生達の帰宅時間かとぼんやり思考しながら、入口へと視線を向けた。入店してきた人物がこちらを向いたので、思いがけず視線が交わる。
「やあ、伊折くん。少しいいかな」
「……劉燐さん。こんにちは」
「こんにちは。姫ちゃんと林檎ちゃんも、少し邪魔するよ」
空いている席──林檎の隣に劉燐が迷わず座る。いつもなら隼人が注文を確認にし来るのだが、今日は何かを察してか彼は焙煎の手を止めずにこちらの様子を窺っていた。伊折も劉燐の用事をすぐに理解し、「どうぞ」と彼女を迎える。
「劉院のお母さんのことなら心配いらないよ。倒れたと言っても階段で少し転んだだけだからね」
「……劉院を騙したの?」
劉燐の突然の告白に、林檎が少しだけ憤りを顕にする。しかし、劉燐は悪びれる様子もなく「そうとも言える」とだけ答えた。
「林檎、落ち着け。……ちゃんと考えがあってのことですよね?」
「もちろん。だって、ああ言えば劉院には家に帰る理由ができるでしょ?」
「それはそうだけど……心配不要ですよ」
「あら、そうだったの?それは余計なことをしてしまったね」
そう言って意外そうな顔をしたが、なんだが嘘くさい。分かって言っているのだろう。食えない人だ。
「隼人さん、アイスコーヒーをお願いしてもいいですか?」
呑気に飲み物を注文する彼女を横目に、姫が不安そうに伊折へ視線を送る。伊折は安心させるように笑ってみせた。しかし、心の中では、まったく笑えていない。隼人によりグラスに落とされる氷の音を聞きながら、頭を冷やす。
「ねえ、伊折くん。自分のせいで誰かが死ぬことを想像できる?」
「……」
「この先、そういったことがあった時に、耐えられる?」
「討伐団員になるには、そのくらいの覚悟、誰だってできてるはずですよね」
「ふふ、そうだね。愚問だった」
「覚悟できてないのはそっちじゃねえか」
「……!」
思いがけない返しに、劉燐が目を見開いた。さっきとは違い、純粋に驚いたという顔だ。
「あいつが傷つくのがそんなに怖いのか?でも、あいつはとっくの昔に覚悟して学院に入学して来てる」
討伐団員の殉職はよく聞く話だ。魔物という幻想生物に抗うには、それなりのリスクがあるのだから当たり前だ。どれだけ人類が不思議な力を有していたとしても、時には敵わないことだってある。それでも、討伐団員は誰かの為にいつも戦っている。そんな団員に憧れて、学院の門をくぐる生徒は多い。
劉院が学院に入学した理由は、そんな志の高い話ではないかもしれない。それでも、誰かのために、一生懸命なのは何も変わらなかった。母のために、覚悟を決めて入学してきたことは、間違いない。
「お待ちどおさん」
隼人が劉燐の目の前にアイスコーヒーを置く。一瞬、彼が伊折に視線を送ったのが分かる。しかし、真っ直ぐに劉燐に向き合っている彼を見て、声をかけるのはやめにした。カウンターへと戻ると、再び珈琲の焙煎や、カップの整理に勤しむ。
「劉院は、まだ守られるべきこどもかもしれねえけど、ちゃんと強くなってるよ」
「どれだけ強くても、ひとりじゃ戦えないよ」
「昨日までの劉院なら、俺も同意見ですよ」
「……劉燐さん、劉院くんとまだ話してないんですよね?」
「あの子はもう昨日までのあの子じゃないわ」
黙って席に座っていた姫と林檎も、劉燐の目を見る。思いがけない自信に、劉燐はへえ、と少し考え込んだ。直後、彼女は寂しそうに笑みを浮かべた。
「やだなあ、何年かけても私達はあの子を救ってやれなかったのに……たった一日で変われるんだね」
「別に俺達はなんもしてないすよ。あいつがどうしようもなくなった時に、たまたま居合わせただけだ」
「……本当は、学院に入学してからあの子が変わったのは分かってたんだ」
アイスコーヒーを一口。氷がカランと音をたてる。
「あの子、お母さんのことばかり気にかけてて、あんまり周りに馴染めない子だったから、すぐに辞めるだろうと思ってたんだ。でも、あっという間に一年が過ぎて、不安になった。本当に劉院は討伐団員になろうとしてるんだって……」
「そんな半端な覚悟じゃないわ」
「そうみたい。だから、私も学院に入学した。あの子を傍で守れるように。……君の言うとおりだ伊折くん。心も身体も傷つく覚悟ができてなかったのは、私達の方」
「だから、お父さんのことも秘密にしてたんですか?」
「……劉院、やっぱり思い出したんだ」
ストローで氷を弄びながら、あーあと小さく呟いた。ついにこの日が来てしまったのだと実感する。
「……あいつのこと、心配かもしれない。気持ちは分かる。俺も、入学前に兄貴たちにめちゃくちゃ反対された」
「へえ、香折先生も反対した?」
「しましたよ。自分は入学したくせに、俺はダメなんて納得いかない。めちゃくちゃ喧嘩した」
「はは、それで今もあんなに喧嘩ばかりしてるんだ」
「……まあ、そうすね。兄貴との喧嘩があれから増えたのは間違いない。でも、俺達の主張も少しは聞いてほしい」
「聞いてあげよう」
氷を弄んでいた手を止めて、顔を上げる。伊折は少し鼻で笑ってわざと視線を逸らした。
「守られるだけなんてごめんだね」
誰に向けての言葉なのかは、その場にいる誰もが理解できた。兄が弟を心配するのは、当たり前のことなのだから。同じように、彼女が劉院を心配するのも当たり前のことだ。それは、伊折も分かっている。分かっているからこそ、劉院の気持ちがよく分かった。
「……心配するくらいなら信じてほしい。俺達は強くなるよ。あんた達を、たくさんの人達を守れるくらいに」
カウンターで傍聴していた隼人が、作業の手を止めて伊折の顔を見た。入学したての彼はまだ小さくて、チームメイトのリョクに身長が負けているのを悔しがっていたのを覚えている。
(気づかんうちに、大きくなったなあ……)
ふふん、と鼻高々に笑う。こどもの成長というのは、あっという間だ。
