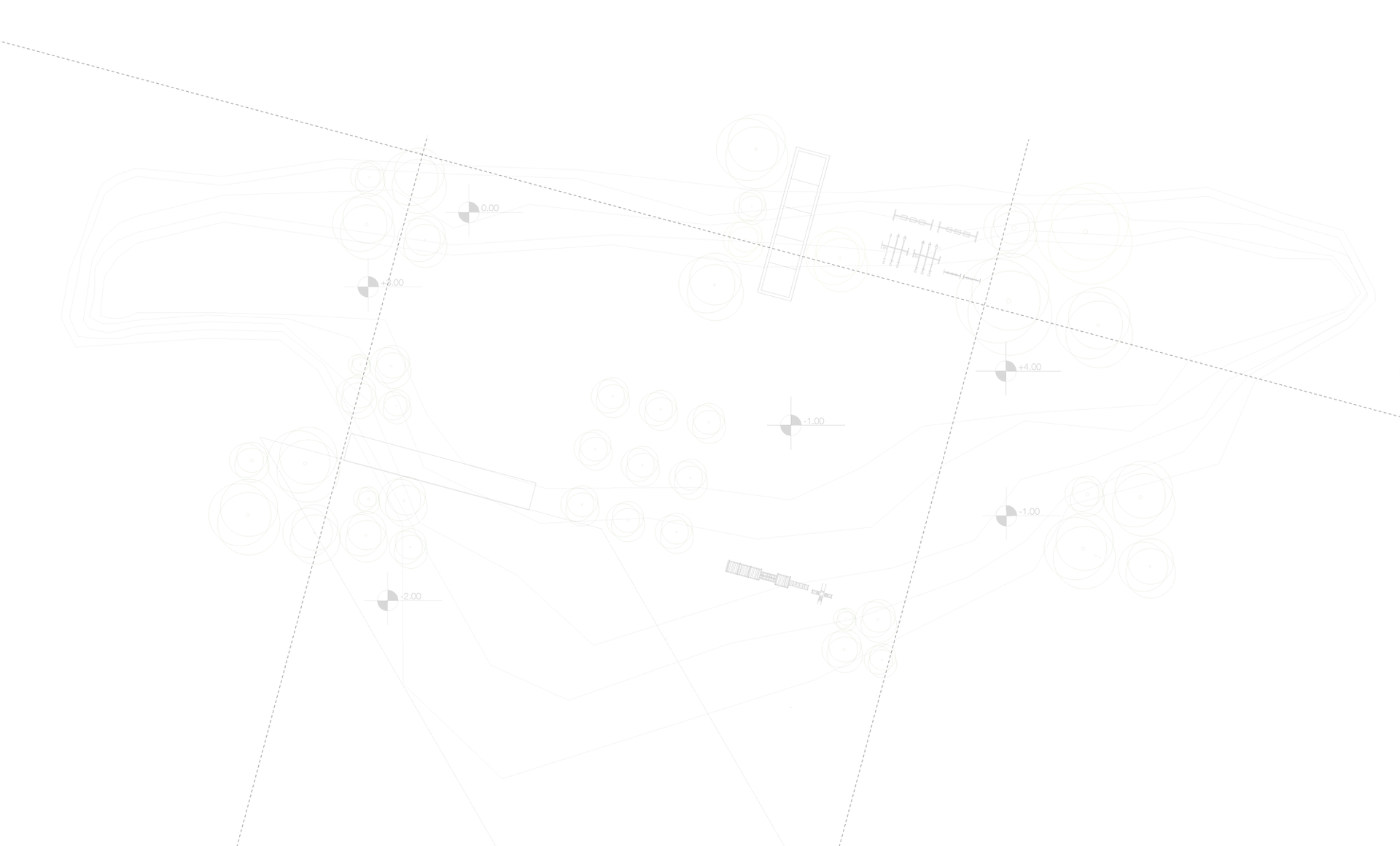
学院から通い慣れた帰路を急ぎ足で辿る。昨日から降り続いていた暴雨は小雨程度に落ち着いたとはいえ、濡れたアスファルトが足取りを重くする。所々、大きな水溜まりが道を塞ぐがそんなものはお構いなしに走るものだから、家に到着した頃には足元が水浸しになっていた。
「母さん……!」
「……劉院?」
荷物を玄関に放り投げて、母の寝ているだろう部屋に駆け込む。劉院の慌てた様子に驚きの声を上げた母は、ベッドの上で本を読んでいた。
「……え?」
「劉院?どうしたのそんなに慌てて」
「劉燐から母さんが倒れたって連絡貰って……」
「それは誤解よ。朝、ゴミを捨てようと思って久しぶり外に出たら、階段で少し躓いて転んだの。今日はいつもより体調が良いくらいよ」
「……怪我は?」
「ちょっと手を擦りむいただけで大事ないわ」
けろっとした顔で、母が手を振ってみせる。確かに、擦りむいたと思われる場所に絆創膏が貼られていた。途端、身体中の力が抜け落ちる。大きく息を吸い、ゆっくりと吐き出した。それは、安堵のため息だった。
「……良かった」
劉燐からの大袈裟な連絡に多少の憤りを感じつつも、安堵の気持ちが勝る。力の抜けた劉院は、母のベッドの横にずるずると座り込んだ。その時、母がベッドの上から劉院を優しく抱きしめた。
「劉院、おかえり」
「……ただいま」
家出してしまったことを怒られるのではないかと思っていたが、母はそんな素振りを一切見せず、いつもどおりの優しい声色で劉院の帰宅を迎え入れた。
「昨日は、心配かけてごめん。母さん、あのさ」
「劉院、ごめんね」
「……」
謝らなくちゃいけないのはこちらだというのに、劉院の言葉を遮るような母の謝罪に言葉が詰まる。
(母さん、違う……違うんだ)
母は、昔から身体が弱いことを気に病んでいた。楽しみにしていた家族揃っての外出に行けなくなった時、家事を手伝えなかった時、劉院の誕生日に入院することになった時、いつも母はこうやって劉院のことを抱きしめて謝罪の言葉を口にする。それが、心苦しかった。
「昨日、私達がお父さんの話をしていたのを聞いたのよね」
「……うん」
「ずっと秘密にしていてごめんなさい」
「母さんは何も悪くない。俺が悪いんだ。謝らなきゃいけないのは、俺の方だろ。母さん、ごめんなさい……俺のせいで、父さんが」
「違うわ!」
今にも泣き出しそうな顔で謝る劉院の言葉を母が遮る。病弱で優しい母から想像したこともない大きな声だった。
「違うの、私が……私がいつもお父さんに頼ってばかりなのがいけなかったの。あの日、私が体調を崩していなければ、一緒にでかけられていれば、劉院の手を繋いでいれば……!」
「……!」
息を飲む。
母はあの日からずっと、自分を責めて続けていたのだ。後悔や、後ろめたさがあるのは、劉院だけではなかった。誰よりも、母があの日のことを悔やんでいたのだ。だからこそ、余計に劉院にあの日の真実を打ち明けられずにいた。
「なんだ……そっか……」
お互いが自分を責めているのだと気がつくと同時に、父が死んだあの日から母にひとりで苦しい思いをさせていたのかと思うと、悔しかった。もっと早く、真実を受け止めて、母の本心をを知るべきだった。彼がすべきことは、ひとりで頑張ることではなかったのだと、気づかされる。
「……母さん、俺の話を聞いて」
母の本音を聞くまでは、己が全て悪いのだと、そう思っていた。今でもその気持ちは変わらない。しかし、母は納得しないだろう。
「俺、なんとなくだけど、あの日のこと思い出したよ」
「……ごめんね、辛い思いをさせたよね」
「もういいんだ。謝らないで。……自分を責めないでほしい。母さんは何も悪くない……悪いのは俺だから……でも、母さんは俺が悪いと思うことを許してくれないでしょ」
「気に病まないで。私、あなたに自分を責めてほしくないの」
「俺も、母さんと同じ気持ちだよ。母さんに自分を責めてほしくない。生まれつき病弱で苦しい思いをしてきたの、知ってるから。母さんが一番辛いよね。だから、母さんも悪くないんだよ。お互い、誰が悪いかを考えるのはもうやめにしよう」
「それは……」
母は俯いた。自分自身を許せない気持ちが痛い程分かる。昨夜、夢から覚めた時、劉院自身もそうだった。許されてはいけないと、そう思った。
母にはこう言ったが、自分を許す気など更々ない。しかし、母はもう充分すぎるくらい長い間、罪の意識を背負ってきたのだ。
これから先は、母の代わりに自分が背負えばいい。覚悟はとっくにできていた。例えこの先、真実を知る誰かから責められることがあったとしても、一緒にいてくれる仲間や友人がいる。彼等はきっとどんなことがあっても味方でいてくれる。それだけで、強くいられる。
「俺、昨日からずっと母さんに謝らなきゃと思ってた。でも、母さんは俺に父さんのことを謝ってほしいわけじゃないんだよね」
「……うん」
「母さん、ありがとう」
「!」
「俺、母さんの子で良かった。いつも苦しい思いしてるのに、一番に俺の事を考えてくれる母さんのことが、俺も大事だよ」
不意に、母の目から涙が零れた。劉院を抱きしめていた腕に力がこもる。
「たくさん心配かけてごめん。でも、もう大丈夫だから。ひとりで頑張るのやめるよ。叔父さん達ともちゃんと向き合う」
「そっか……うん。お母さんも、ごめんね。劉院の頑張ってる姿を否定したくなかったの。でもね、本当は一緒に頑張りたかった……」
母は誰よりも劉院のことを案じていた。本当は、誰よりも彼と一緒に前を向きたいと思っていた。
その姿は紛れもなく、こどもを愛する母の姿だった。
「もっと早く、ひとりで頑張る必要なんてないって、教えてあげれば良かった」
「俺も、もっと早く気づけばよかった」
「お互い、ちゃんと話すべきだったのね」
「うん……」
ばかだねと言って、笑いあう。
その姿は、どこでにもいるお互いを想いあう親子だ。ずっと、こうして本当の家族になりかった。それが、ようやく叶った気がした。
