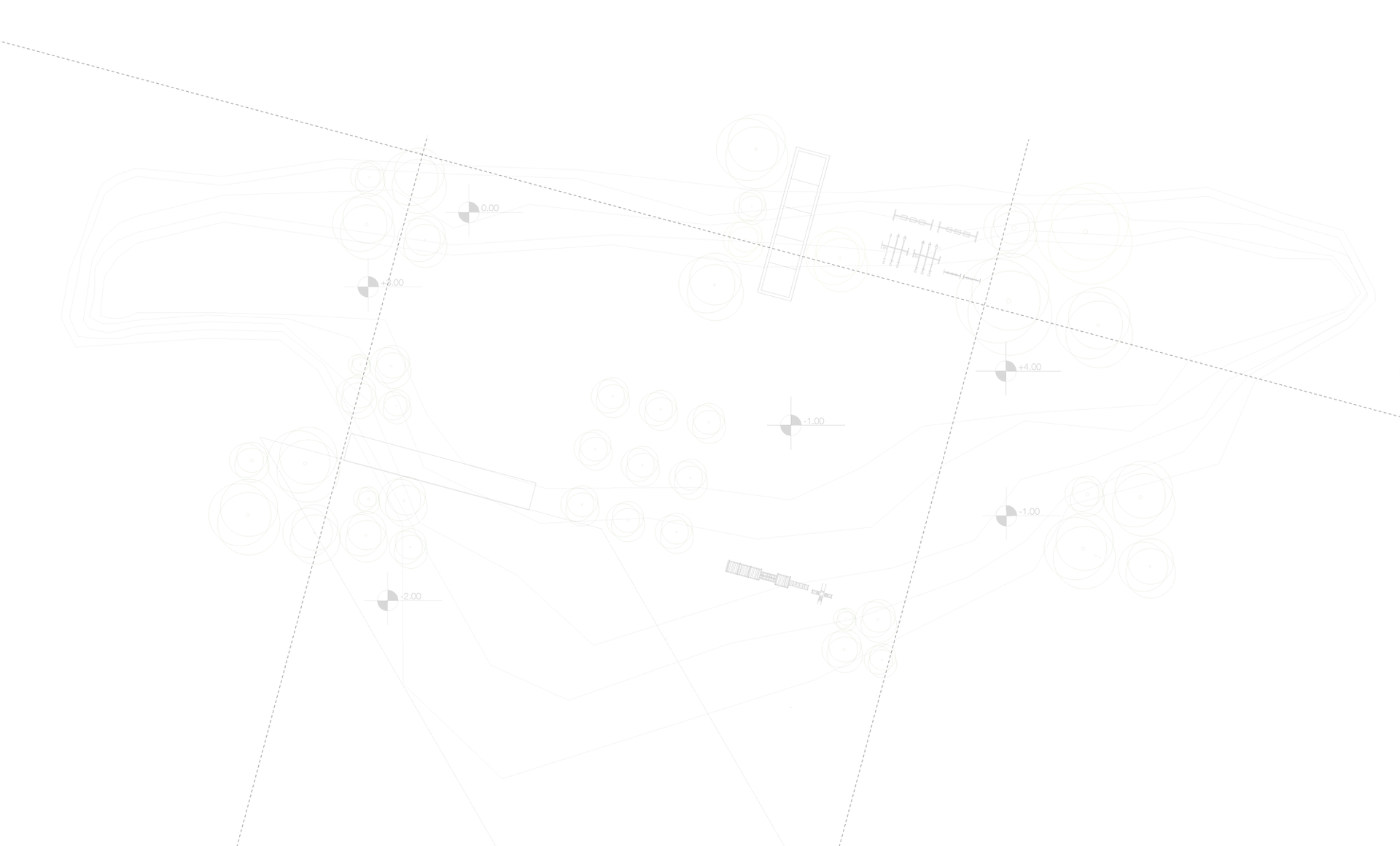
「家出!? あんたが!?」
食堂に林檎の驚きの声が響き渡る。同時に、周囲の生徒達が一斉にこちらへと視線を向けた。慌てて、声がでかい!と伊折が彼女の口を塞ぎながら、視線を向ける生徒達に向かって適当に笑顔を振り撒く。
「あはは、えっと、お騒がせしました……」
「ああ、箕原か」「どうせ香折先生と喧嘩したんでしょ」なんていう声がそこかしこから聞こえてくる。そんな周囲の反応に、伊折が思わず頭を抱えた。
「俺の印象ってどうなってんの?」
「あんた、香折先生と校内で喧嘩するのやめなさいよ」
「だって兄貴が……いや、今は俺のことはいいんだって」
やるせなさにため息をついてから、弁当箱を広げる。彩り豊かなそれは、いつもどおり次男が腕によりをかけて作ったものだ。いつもと違う点は、劉院が伊折と同じ弁当を広げていることだった。
「それで、昨日は伊折さんのお家にお泊りして、一緒に登校して来たんだね……意外だったからびっくりしちゃった」
「そんなつもりはなかったけど、香折先生が一緒に行けって言うから……」
「別々に行くのも変だろってさ。まあ、確かにそうなんだけど……兄貴は時々空気が読めないから。あと、佐折兄ちゃんの前ではお互いあんまり邪険にはできねえっていうか……」
箕原家に一晩お世話になったあと、すぐにでも家に帰ろうと考えた劉院だが悔しくも今日は平日のため、学院の登校日である。教師の目前でサボるわけにもいかず、仕方なくそれは放課後へと持ち越されることになった。
そのため、伊折と劉院が一緒に学院へ登校するという、一部の人間に目を疑われるようなことが実現した。そんな有り得ない光景を目にし、誰よりも驚きの声を上げたのはチームメイトである林檎と姫の二人に他ならない。
「佐折さんの前じゃなかったら断固拒否してたとこだ」
「昨日の素直さどこいった……?同一人物?」
「調子にのんな」
佐折の詰めたおかずをつつきながら、いつもどおりの会話ができていることにほっとする。林檎や姫の手前、変な気を遣ってくるかと思っていたが、伊折の態度は普段と何も変わらない。むしろ、いつもどおりすぎるくらいだ。そんないつもどおりの二人の目の前で、事情を把握した林檎と姫は、驚きの表情を浮かべる。
「あんた、変わったわね。この間、伊折の手を払いのけてたとは思えないわ」
「それは……」
「いいのよ、私は嬉しいくらい。あんたってば入学してからずっと、俺のことは放っといてくれって態度だったんだもの。こう言ったら、気を悪くするかもしれないけれど……ちょっと心配だったのよね。でも、あんたがそれを嫌がってることは分かってたから、私も少し突っぱねすぎたわ。ごめんなさいね」
林檎が申し訳なさそうに謝るので、思わず動揺して視線が泳ぐ。しかし、それではいけないと思い直し、改めて彼女に視線を合わせる。謝るべきは、こちらの方だ。
「無駄に心配かけた俺が悪かったと思う……ごめん」
今なら、林檎の言いたいことがよく分かる。頼れるのは自分だけだと思い込み、チームメイト達の手を払いのけてきたのは、劉院自身なのだから。周囲の大人たちだけでなく、チームメイトにまでいらない心配をたくさんかけてきた。
「気を遣われるのが嫌だったし、心配されるのも、こども扱いされてるみたいで悔しかったんだ。でも。真実を知ってやっと思い知った。俺はまだまだこどもだ」
「……確かに、私達はまだまだこどもだと思う。ひとりじゃ、できないことも多いよね。でも、劉院くんの今までの頑張りは、なにひとつ無駄じゃなかったと思うよ」
「そうかな……」
「うん」
姫が、真っすぐに劉院の目を見て微笑む。今まで劉院のしてきたことは、周囲の人間を酷く心配させたのは間違いない。しかし、母のために不慣れな家事を頑張ってきたのも、将来のために討伐団員を目指したことも、決して間違ってはいなかった。劉院の失敗は、全てをひとりで成し遂げようとしたことだ。
「それにね、私、入学したての頃に劉院くんに背中を押してもらえたから、今もこうやって一緒に頑張れるんだ」
入学したての頃、二年前のことを思い出す。入学したての姫が、今と比べるとかなり暗い性格だったのは記憶に残っている。長い前髪で表情を隠し、常にオドオドしている気弱な少女だった。そんな彼女が気に入らなくて、前髪を切り、長い髪を結うように勧めたのは劉院だった。背中を押したつもりはまったくない。
ただ、あの頃の劉院は、少し気が立っていて、こんな奴とチームメイトだと知れたら叔父に心配されると思ったのだ。自分のためにやっただけにすぎないため、思わずばつの悪い表情を浮かべる。
「いや、あれは……」
「劉院くんにとっては、あんまりいい思い出じゃないかもしれないけど、あの日、劉院くんにきっかけを貰ったんだ」
「きっかけ……?」
「前髪を切るのも、髪を結うのも、劉院くんに言われたから、怒らせないようにしなきゃって思ってやったことなの。でもね、次の日から、世界が変わったんだ。変じゃないかな、何か酷いことを言われないかなって不安だったけど、周りの皆がそっちの方がいいって言ってくれたし、皆の顔がよく見えるようになってから、私からも声をかけられるようになって……少しずつ周りに打ち解けられるようになって……」
二年前のことを振り返りながら、懐かしそうに姫が言葉を綴る。劉院も、同じように当時のことを思い浮かべた。あの頃の劉院は、一番周囲を威嚇していたのだが、姫はそんな彼を少し怖がりながらも、好意的に思っていたのはなんとなく知っている。怖がりながらも離れようとはしない、変な奴だと不思議に思っていたことを思い出す。その理由を今、初めて知った。
「私、学院に入学するまで友達がほとんどいなかったの。でも、ちょっとしたきっかけひとつで、今こうしてたくさんの友達に出会えたから……劉院くんが、この学院に入学してくれて良かった。劉院くんの頑張りのおかげで、変われたんだね、私。ありがとう、劉院くん」
少しだけもじもじしながら、そう言った姫を林檎が思わず抱きしめた。姫は、小さく驚きの声を上げたが、照れくさそうにその手を重ねる。劉院の頑張りは、本人の気づかないところで誰かのためになっていた。それは、劉院にとって思いがけないことだった。
「姫……!ずっと、ずーっと友達よ!」
「ふふ、ありがとう林檎ちゃん」
「そんな気はなかったけど……まあ、お前がそれでいいなら」
「うん。劉院くんとも、ずっと友達でいたいな」
「……まあ、いらねえ心配だろ」
「ふふ、そうだね。劉院くんも、ちょっとしたきっかけひとつで、変わったんだよね。お父さんのことは、辛い事実だったかもしれないけど……きっと、今からでも間に合うよ。もし、家に帰ってまた何か辛いことがったら、今度は私のことも頼ってくれると嬉しいな」
「おう……ありがとな」
こうやってチームメイトと身の上話をしたのは初めてのことで、少しだけ照れくさい。それは、他の三人も同じだったようで、その後はたどたどしい会話が続いた。しかし、それも次第にいつもどおりの会話へと切り替わる。
劉院と林檎がちょっとした悪態をつけば、伊折がそれを咎め、姫が最終的に仲裁をする。いつもなら、そこで終わっているはずの会話が、今日はなんだかんだでその後も続いた。二年間、なんとなく踏み込めずにいたお互いの境界線が、少しずつ消えていくのが分かる。劉院にとっても、姫にとっても、大切な居場所になっていた。
四人で他愛もない言葉を交わしながら、穏やかな昼休みを過ごす。そろそろ午後の授業の準備に取り掛かろうかと食堂を後にするため身の回りを片付け始めた頃。不意に、劉院の携帯に一件のメッセージが届く。それは、従姉である劉燐からだった。
「……伊折、悪い。早退してもいいか?」
金曜日の午後は、いつも対抗戦に参加していた。それが、今日は叶いそうにない。
「……どうした?」
「母さんが、倒れた」
携帯の画面を見つめながら、劉院の顔が酷く曇る。少しだけ、手が震えていた。
(俺が、余計な心配をかけたからだ……)
「劉院くん」
「劉院」
「……劉院」
三人に、名前を呼ばれる。姫が劉院の手を握り、伊折が肩を抱く。林檎は彼の頭を優しく撫でた。
「あんたのせいじゃないわ」
「大丈夫、誰も劉院くんを責めたりしないよ」
「お母さんのとこ、行こう」
「……うん」
チームメイトが支えてくれる。それだけで、酷く安心した。
ひとりで背負い込むのは、もうやめにしよう。
