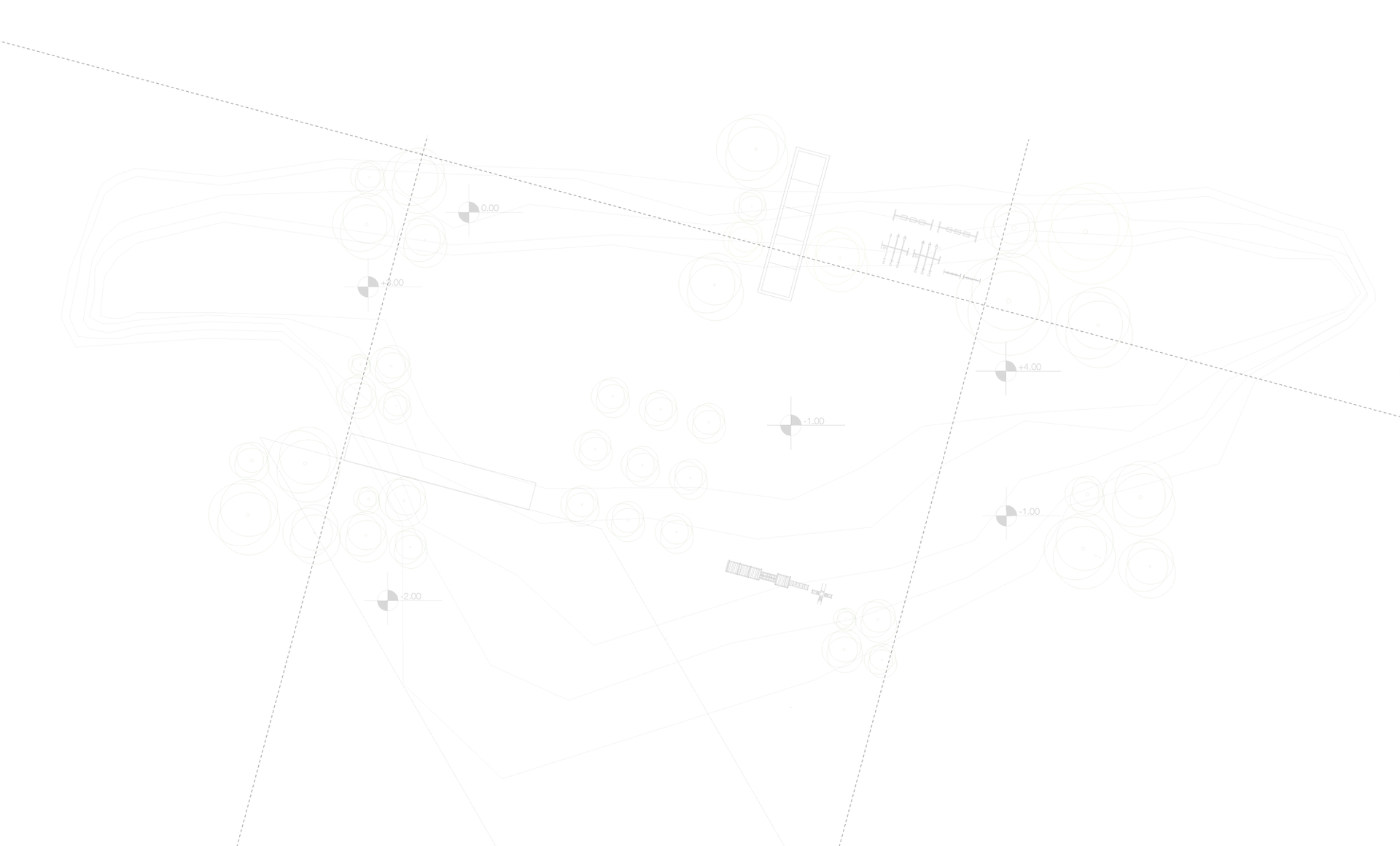
雲一つない晴天を見上げて、首をかしげる。こんなに天気のいい日は何日ぶりだろうか。六月に入り、例年より少しだけ早く梅雨入りしたというニュースを見たのはいつのことだったか。しばらく、梅雨らしいじめじめとした日々が続いていた。
しかし、今はどうだろうか。からっと晴れた空と、蝉の声。じんわりとした汗が頬をつたう。
(……夢か)
ひと月ばかり早い夏の空気と、見覚えのある光景に、劉院は自分が夢を見ているのだと理解した。
劉院は、大きな雑木林に囲まれた道に立っていた。見覚えがあるのは、幼いころ──まだ父が生きていたころに、何度も連れて行ってもらった記憶があるからだ。
森林の中に、こどもたちが楽しめる公園があったのを覚えている。その公園にある、長いすべり台が大好きだった。父と一緒に、長い階段を一生懸命のぼると、母が留守番しているはずの自分の家が遠くに小さく見えるのだ。それを指さして、次は母さんと一緒にすべりたいと言って父を困らせたこともある。父のことは、あまり多く覚えていないが、この森林公園でたくさん遊んだことだけは、よく覚えていた。
(ここ、どこだっけ)
周囲を見渡し、自分が森林公園のどこにいるのだろうかと思案する。蝉の声がやけに大きく、人の気配がしない。世界にひとりぼっちになってしまったかのような感覚に、不安を覚える。しかし、そんな不安をかき消すように、蝉の声に交じってキュッという小さな鳴き声が聞こえた。
「……お前、どこから来たんだ?」
小さな鳴き声の聞こえる方へと視線を向けると、劉院の足元に一匹の小さなリスがちょこんと座っていた。もう一度キュッと鳴くと、リスは劉院の足をよじ登り始める。慌てて、落とさないようにリスを拾い上げると、劉院の手の中でちょろちょろ動き始める。そんなリスを見ていると、なんだか懐かしい気持ちがこみ上げてきた。
(俺、こいつとどこかで……)
会ったことがあるような気がすると思考した時、突然リスが劉院の手から飛び降りた。数メートル先へ着地したリスが、劉院の顔色を窺うように、キュと鳴く。同時に、突然、妙な胸騒ぎがした。ついてこい、と言われているのがなんとなく分かる。しかし、この先に向かうのであれば、覚悟をしろと言われているようにも思えた。大切なことを忘れている気がする。ふと、森林公園での父との記憶が蘇る。
『劉院、あまり一人で先に進んではいけないよ』
『そんなに急かさないで。すべり台は逃げないから』
『リス? 劉院、待って。どこに行くの? 劉院!』
父の声が、木霊する。
「……父さん?」
はっと顔を上げて、後ろを振り返る。しかし、そこには誰もいない。もう一度、リスの進もうとしている方向に、視線を向けた。すると、そこにリスの姿は既になく、代わりに、黒く大きな生き物が、こちらを睨みつけていた。それが、魔物であることはすぐに分かった。
「ッ……!」
瞬時に、後ろへ飛びのき、体制を整える。己の武器である槍を探して、腰に手をかけるが自分自身が今手ぶらであることを思い出した。同時に、突然地面との距離が縮まる。身体が思うように動かない。何故、と思案するよりも早く、自分自身の手がとても小さくなっていることに気が付いた。
(こどもの頃の俺だ……)
魔物が大きな咆哮を上げた。同時に、大きな口を開けてこちらへと向かって突進してくる。この小さな身体では、避けることは不可能だ。
──劉院!!
不可能なはずだったのだ。
懐かしい声が、劉院の名を呼んでから、小さな身体を抱きしめる。それが、父であることを思い出したのはその時だった。
(そうだ俺……あの日……!)
父のぬくもりを思い出すと同時に、はっと目が覚める。冷や汗が背中をつたい、心臓が激しく動悸する。
(ああ、なんとなく……思い出した)
あの日、父といつも通り森林公園に遊びに来ていた劉院は、すべり台に続く階段をのぼっている最中に、リスを追いかけて父とはぐれてしまったのだ。はぐれてしまった先で、魔物に襲われた。どうしてあの場所に魔物が出没したのかは分からないが、そんな劉院を守るために、父は死んだのだ。
「やっぱり、俺が殺したんじゃねえか……」
現実が、劉院に重くのしかかる。母は、叔父は、劉燐は、真実を知っているのだろう。
どうして、こんなに大切なことを忘れてしまったのだろうか。小さな劉院に、この現実は耐え難いものだったのだろうか。まだ、たったの五歳だったのだから当たり前だ。そうだとしても、全てを忘れて、母のためだと思い込み、周囲の人間から距離を置いてき自分が憎たらしい。
自分の今までの行いが正解だとは思っていなかったが、全て自己満足でしかないのだと、ようやく気が付いた。そんな劉院を気にかけてくれている叔父たちが、いつまでもこども扱いをしてくるのも頷ける。
「……劉燐の言うとおりだ」
周囲の優しさを跳ねのけて、自己満足していた己は、間違いなくこどもだった。現実を受け止めて、今自分が何をすべきなのか、よく考える。ここで、ただ落ち込むだけでは何も変われないのだ。
「ん……劉院? 眠れねえ?」
劉院のために敷かれた布団の隣で寝ていた伊折が不意に目を覚ます。目をこすりながら、心配そうに劉院の顔を覗き込んだ。
「……ちょっと夢見が悪かっただけだ。大丈夫だから」
「劉院って、嘘つくのが下手だよな。顔色、悪いぜ」
「……なあ、伊折」
「うん?何……?」
眠気に負けかけているのか、ウトウトしながら相槌を打つ。気にせず寝てしまえばいいのにと思いつつも、頑張って劉院の言葉に耳を傾ける伊折に話しかけた。
「もし、この先……俺のせいで、誰かが死んだらどうする?」
「え? なんで? うーん、そうだな……」
眠気のせいで質問の意味がよく分からないらしい伊折が、首をかしげながら、枕に顔を埋める。そのまま寝てしまうかと思ったが、なんとかもう一度顔をこちらへと向けた。
「そんなことは、多分、ない……と思う……けど。もし……」
「……寝ていいぞ?」
自分で問いかけておきながら、答えを聞くのが急に怖くなる。思わず、寝るように促すと、うんと小さく頷きながら、伊折が目を閉じる。
「……そうなったら、一緒に背負ってやるから……だい、じょ……ぶ……。そのための……チームだから……」
すぅと小さな寝息が聞こえる。完全に寝落ちたらしい。
「一緒に……か」
伊折の言葉が、少しだけ劉院を安心させた。学院に入学するまで、いつもひとりぼっちの気がしていた。周囲に頼れる人間はいない。そう思い込んでいた。
いつからだろうか。学院に行けば、伊折や林檎、姫──チームメイトがいて、航琉のような親友と呼べる友達もできた。気が付けば、ひとりぼっちだと感じることは少なくなっていた。
学院への入学は、劉院自身の自己満足だったかもしれない。それでも、入学して良かったと言える。それだけは、叔父にも分かってほしいと思った。
「……俺も寝よう」
母と、叔父に今伝えるべきことがなんとなく分かった気がした。己の罪を受け入れて、謝ろう。そして、これからのことを話し合おう。
覚悟を決めて、目を閉じる。伊折の寝息が、やけに心地よく感じるのは、彼を信頼しているからだろう。本人には内緒だ。どうせ、すぐ調子にのるんだから。
