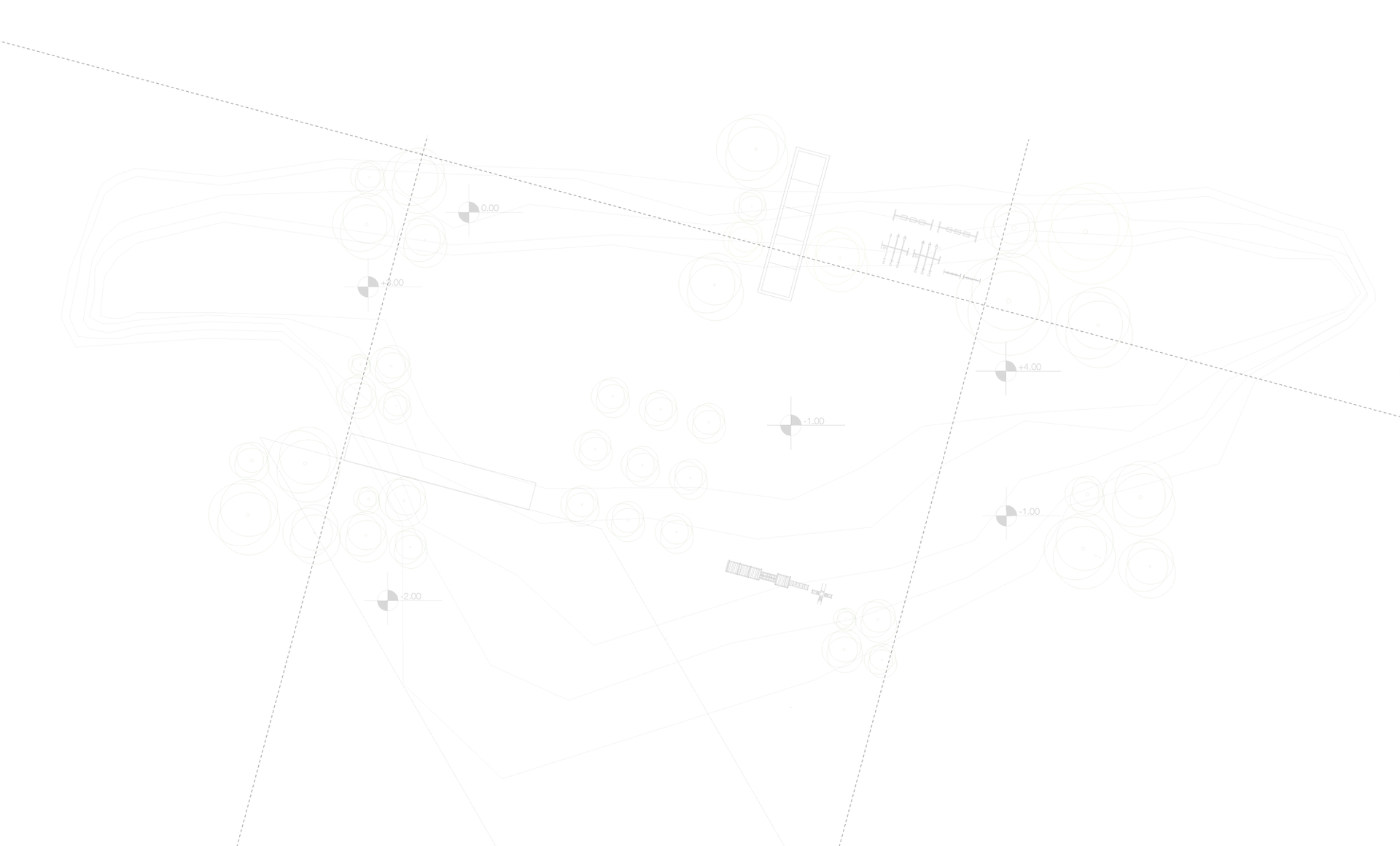
「君が劉院くん? 伊折からよく話を聞いてるよ」
「こいつ、佐折。うちの次男」
伊折の提案で急遽、箕原家に世話になることになった劉院を笑顔で迎えたのは次男の箕原佐折だった。黒い髪と青い瞳は伊折と香折とお揃いだが、二人に比べたら温和な雰囲気の優しそうな青年だった。
「よろしくね、劉院くん。今日はゆっくりして行ってね」
「その、突然すみません」
「いいのいいの! 今日は父さん達が仕事で留守だからちょっと寂しかったんだ。賑やかになって嬉しいよ! あ、夕飯はカレーなんだけど嫌いじゃないかな? 甘口と辛口どっちが好き? 伊折は甘口が好きなんだけど、香折兄ちゃんは辛口が好きだから、どっちも用意してるんだ。好きな方を選んでね!」
「え、あ、その……」
「佐折兄ちゃん!劉院、戸惑ってるから!」
二人に比べたら落ち着いていそうだと思った第一印象はすぐに覆されることになった。押しつけがましくない程度に騒がしい。二人にそっくりだ。
「あ、驚かせちゃってごめんね。伊折が友達を連れてきたのが久しぶりだったからつい……」
「佐折兄ちゃん、やめて。俺ちょっと恥ずかしい」
「ええ、なんで? 昔はあんなにたくさん友達を連れてきてくれたのに最近はあんまりだよね。緑依くんは元気? また遊びにおいでって言っておいてね」
「元気元気。そりゃもう元気だよ」
学院では見たこともない伊折のタジタジな姿に、劉院は少しだけ驚いた。学院ではあまりこうやって年上に振り回されている姿を見ることはなかったからだ。そもそも、兄の香折の存在から弟であることは知っていたが、彼が三兄弟の末っ子であることすら、今日初めて知ったのだ。お互いのことをまだまだよく知らないのだと気が付くには十分だった。それは、少し前から伊折も気がついていた。
「お前らそこまでにしとけ。冷める前に飯食おうぜ」
「はーい。すぐ用意するから劉院くんはゆっくりしててね」
「俺、手伝いますよ。その……良かったら手伝わせてください」
「……じゃあ、お願いしようかな」
慣れない他人の家でじっとしているのが申し訳なくて、手伝いを名乗りでる。佐折が少し思考してから、それを快く受け入れてくれたため、ほっと胸をなでおろした。劉院の気持ちを察してくれたのだろう。そういうところも、二人に似ている気がした。
「じゃあ、ご飯よそってもらってもいいかな。量は適当で大丈夫。いつも足りなければおかわりするし。劉院くんも遠慮せず好きな量をよそってね」
「分かりました」
キッチンに用意されていたお皿に言われたとおり、適当な量を盛る。佐折はその隣で手際よくサラダを取り分けると、伊折を呼んでリビングに持っていくよう指示を出した。
「カレー、どっちにする?」
伊折と香折の分にカレーを盛りつけながら、佐折がもう一度聞く。家では母の胃に刺激を与えないようにいつも甘口を作っていたため、劉院は少し遠慮気味に甘口で、と答える。
「いつも二人の好きな味に合わせて作ってるんですか?」
皿を手渡しながら、黙っているのも変な気がして、こちらから会話を振ってみる。忙しい母に代わって、箕原家の料理はいつも彼が担当しているらしい。
「うん、我が家はいつもそうだよ。あの二人、そっくりなのに好みは意外と違うんだよ。やっぱり、兄弟でも似てないとこはあるよね」
「面倒じゃないすか?」
「……香折兄さんがよく言うんだよね。俺のことはいいから、伊折の好きなもの作ってやれって。長男だから、いつも弟に譲るのが当たり前だと思ってる。香折兄さんらしいけど」
「なんとなく分かります」
学院内で伊折と香折が喧嘩しているのをよく見かける。あの兄弟は仲が悪いと思われることもあるようだ。しかし、香折が伊折のことを気にかけているのは、よく見ていれば分かることだった。長男らしく、弟を気にかけている優しい兄の姿だ。そんな二人を少しだけ羨ましいとさえ思ったこともある。
ひとりっ子だった劉院にも、劉燐という従姉がいたが、彼女とは姉弟ではない。劉燐は、劉院のことを本当の弟のように思ってくれているのかもしれないが、やはりその好意を素直に受け止められずにいるのは、自分が彼女にとって良い弟になれるとは思えないからだ。いつか、素直に受け止められる日はくるのだろうか。
「優しい香折兄さんのために、好きな物を作ってあげたいなっていう僕の我が儘で作ってる。だから、好きでやってるんだ」
「佐折さんも優しいんすね」
「ふふ、ありがとう。でもね、伊折も優しいんだよ。いつも家事を手伝ってくれるし、寂しがりやな僕とたくさんお話してくれる」
「……知ってます。いつも、世話になってるので」
お互いのことを大切に想っている、優しい兄弟だ。両親は不在なことが多いらしく、寂しい思いもしてきたようだが、劉院にとっては眩しいくらいの、仲のいい家族だった。
(普通の家族ってこういうもんなのかな……)
羨ましいと思うのは、母に悪い気がした。しかし、少しだけ憧れがあるのも事実だった。もし、父が生きていたらと、願っても無駄なことを想像してしまう。その父が死んだのは、自分のせいだというのになんておこがましいのだろうか。
「劉院くんも、家ではよくお手伝いをするんでしょ?手際がいいもんね」
「……はい。母さんは身体が弱いから。母さんも、たまに調子のいい時は手伝ってくれるんですけど、なんか心配で、結局全部俺がやってます」
「お母さんのことが大好きなんだね」
「え?」
「あれ、違った?」
母のことを話して、そう言われたのは初めてのことだった。大変だね、偉いね、と気遣いの言葉ばかり掛けられてきた劉院にとって、その言葉は思いがけないものだったため、思わず驚きの声が上がる。
「……いや、違わない……です」
「劉院くんも、優しいね。誰かのために頑張れるのは、凄いことだよ。それが、たとえ家族だとしても、当たり前だとは限らないもんね」
「じゃあ、佐折さんも凄いってことすね」
「うん、僕って凄いの。でもね、たまに疲れることもあるでしょ? そういう時は、いつでも頑張るのをやめてもいいんだよ。劉院くんも、疲れたら休んでね。もし、休める場所がないなら、またうちに遊びにおいで。僕はいつでも大歓迎だから。」
青く澄んだ優しい瞳が劉院を捉えながら微笑む。温かい視線が、少しだけむず痒いが、不快ではない。少し照れながらも「ありがとうございます」と答えると、彼は嬉しそうな表情を浮かべながら綺麗に盛り付けたカレーを持ってリビングに向かった。
「なあ、佐折兄ちゃんなんか劉院のこと丸めこもうとしてねえ? そうやってすぐ俺の友達をうちの子にしようとするのやめてって言ってるじゃん!」
「あはは、伊折にバレちゃった。ざんねーん」
後を追ってリビングに向かうと、伊折が慌てて劉院を手招く。隣に座るように促してから、聞こえていたらしい会話を咎めた。そんな伊折を抑制しつつ、劉院は小声で話しかける。
「なあ、佐折さんにどこまで話した?」
「え、俺喋ってねえよ? 兄貴も多分なんも言ってない。友達を呼ぶとしか伝えてないから安心しろよ」
「……そっくりだなお前ら」
「たまに言われるんだけど、そんなに?」
「似てる。でも、ちゃんと違うとこもあるよ。甘口が好きなんだな」
「揶揄ってる?」
「大丈夫、俺も甘口好きだよ」
「揶揄ってんじゃん!」
そっくりな三人だが、察しの良さは次男が断トツらしい。彼の作った甘口のカレーは、劉院が作るカレーよりも更に甘かった。
