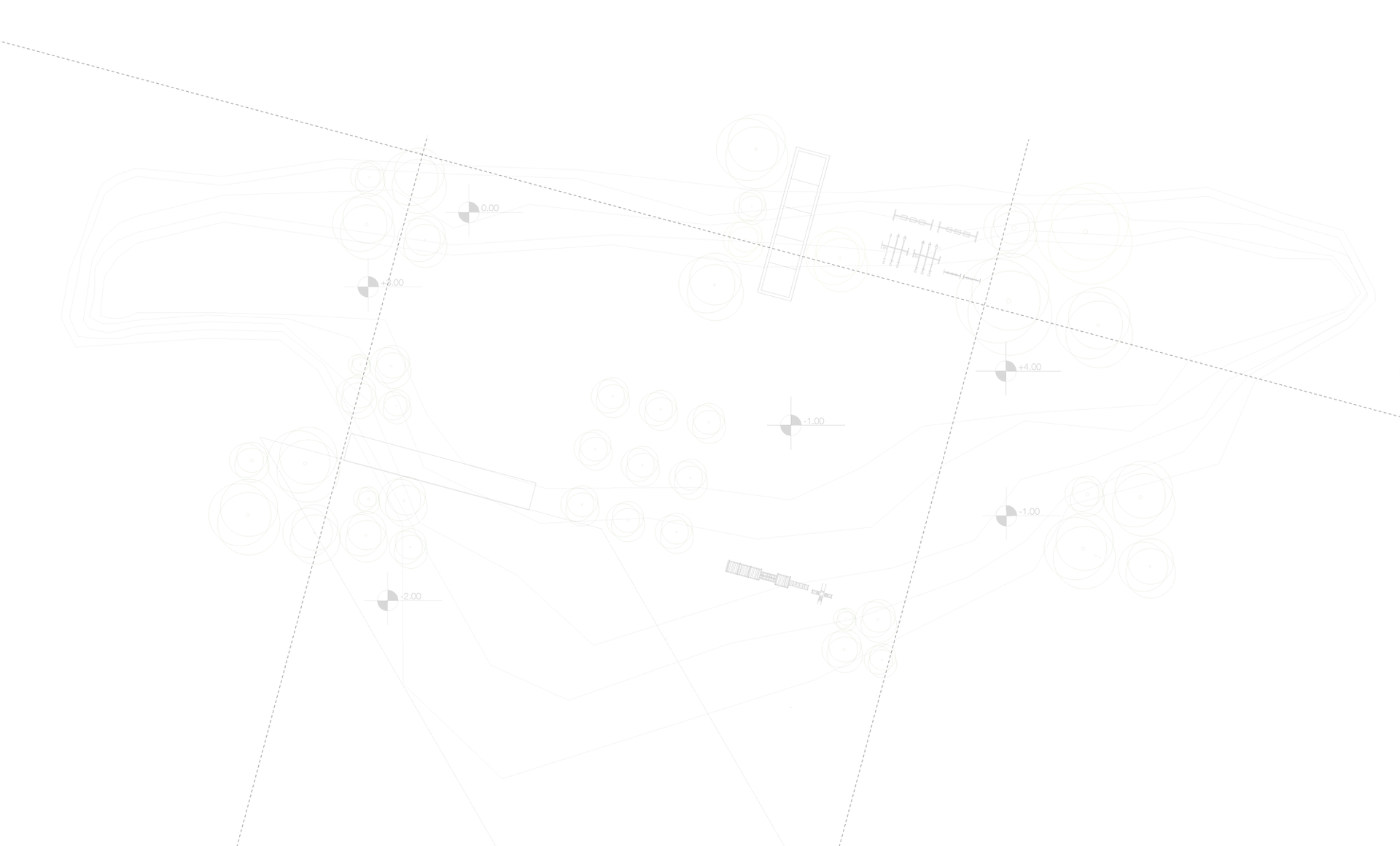
「つまり、家出してきたのかお前」
はっきりと言われてしまい、肩身が狭い心持ちに、思わず目をそらす。ぐっと言葉に詰まると、突然パァンと大きな音が部屋中に響き渡った。次の瞬間には、頭を抱えてテーブルにつっ伏す香折の姿があった。
「いってえ……!何すんだ隼人!」
「ほんっまにデリカシーのない男やな!」
どこにそんな物があったのか、いつの間にか隼人の右手に握られているハリセンに目を丸くしていると、隣で話を聞いていた伊折が乾いた笑みを浮かべる。
「今のは兄貴が悪い」
「……悪かった」
「いや……そのとおりなので……」
香折の言うことは何も間違ってはいない。不可抗力で知ってしまった真実に衝撃を受けて、家を飛び出してきたのだから、家出と大差ないだろう。気持ちが整理できるまでは母に合わせる顔もなく、できることならば家に帰りたくないと思っているのも事実だ。
(帰りたくないなんて……初めて思ったな……)
片親であることを哀れに思われる事は時々ある。片親なんて、今どき珍しくもないのだが、母の身体が弱いためか、いつも大変だねと気を遣われてきた。嫌になることもあるだろうと言われたこともある。しかし、そんなふうに思ったことも、家に帰りたくないと思ったことも一度もなかった。
周りからなんと言われようと、劉院にとって母は唯一の家族だったから。自分が支えるのは当たり前のことで、それが普通だと思っていた。しかし、その当たり前を母がどう思っているのかは知らなかった。今は、母の本音を聞くのがなによりも怖い。
「家出なんて劉院くらいの年頃には割とようある話やさかい、そんなに思いつめる必要あれへんで。俺にも経験ある」
「隼人さん、家出したことあるんすか?」
伊折の意外そうな口ぶりに、隼人は笑いながらあるよ、と言ってからそういえば……とふいに考える仕草を見せた。
「親の反対押し切って学院に入学したまま帰っとらんから今も家出中みたいなもんやな」
「お前、親父さんと仲悪いよな。たまに電話してると思ったらめちゃくちゃ怒鳴りあってるし」
「あはは、お前はなんも反省しとらんなあ」
先程よりは軽いが、それでもしっかりとハリセンの叩きつけられる音がもう一度響き渡る。今度こそ反省したのか、これ以上は何も言わん、という顔で香折が唇をぎゅっと噛み締めた。それがなんだかおかしくて、劉院は思わず吹き出してしまった。
「うん、ちょっとはマシな顔になったな」
「……あ」
吹き出した劉院の様子に、香折が安心した顔を見せると、はっと気がつく。いつの間にか、ぐちゃぐちゃになっていた気持ちも落ち着いていた。少しだけ、いつもどおりの自分に戻れた気がする。
「でも、できればまだ帰りたくないんだろ?」
「それは……」
「遠慮しなくていいんだぞ。言ったろ。頼ってくれたら、俺はそれに応えるよ」
香折の問いかけに、再び言葉を詰まらせると伊折が劉院の肩をポンポンと優しく叩いた。一度、伊折の目を見る。その目は、真っ直ぐ劉院のことを見ていた。嘘偽りのない、澄んだ青い瞳だ。
「……少しだけ、時間がほしい。その、母さんと向き合うために、気持ちを整理したい」
少しだけ戸惑いながらも思ったことを言葉にすると、隼人が「そっか」と頷いた。香折が「いいと思うぜ」と答える。そして、伊折が「よし!」と突然立ち上がった。
「じゃあ、決まりな!兄貴、こいつ今日うちに泊めていいだろ?」
「え?」
突然の提案に、劉院は目を丸くした。確かに、行く宛てがないのは事実だが、まさかチームメイトの家に泊まるなんて思いつもきもしなかった。
「いいぜ。どうせ親父たちも留守だし、佐折も喜ぶんじゃねーか? 親御さんには俺から連絡してやるよ。そこは教師の務めだな。」
「ええやん。劉院、そうさせてもらい。香折の家が嫌ならうちでもええよ」
「いや、でも……」
そこまでしてもらうのはなんだか悪い気がして、視線を泳がせる。すると、伊折が先程よりも少しだけ強引に肩を叩いた。それが少しだけ鬱陶しくて、思わず普段と変わらない冷たい態度をとってしまう。
「友達の家に遊びに行くと思えばいいんだって。たまにはいいだろ?」
「お前……やっぱり少しは遠慮しろ」
「お、いつもどおりの劉院だ。でも、今日は遠慮しないって言ったからな!」
いつもどおり、嫌な顔など一切見せずにそう言って笑う。この男がそんなお人好しであることは、とっくの昔に知っていた。
