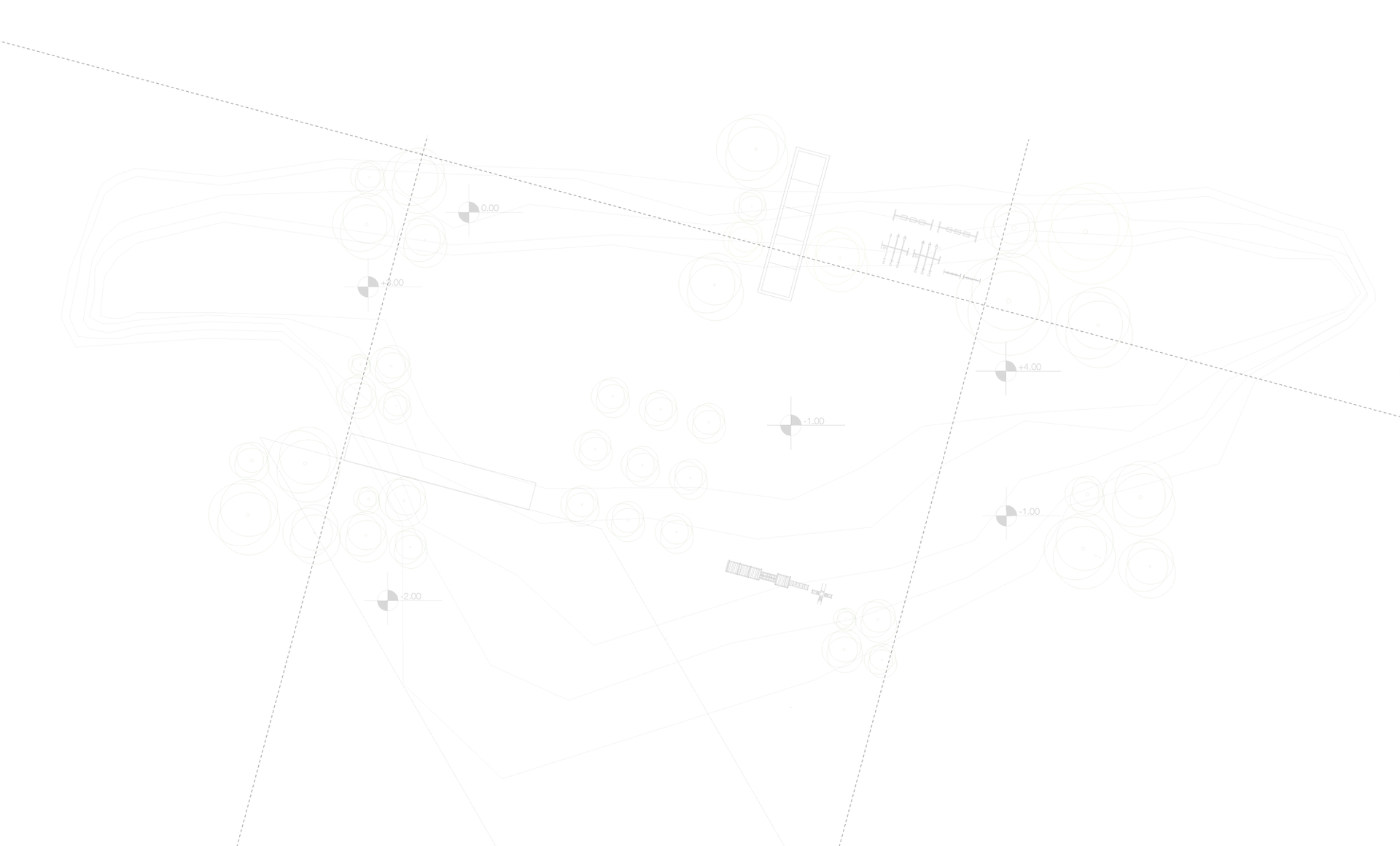
父が誰かを庇って死んだということは知っていた。小さい頃、突然父がいなくなって戸惑った劉院に、周りの大人たちがいつも言っていたからだ。
『君のお父さんはね、″大切な人″を守ったかっこいいお父さんなんだよ』
『だから劉院が悲しむ必要はないんだ』
『何も気にしなくていいのよ。心配いらないからね』
全て己のための建前だったのだと、初めて知った。いや、何故気づかなかったのだろうか。いつだって大人たちは、″大切な人″を守って死んだのだと言っていたのに。
父の大切な人が誰なのかと考えたことがなかったわけではない。しかし、なんとなく知りたくないと思っていたのも事実だ。わざとその真実から目を背けて曖昧にしてきたのだと、ようやく気がついた。劉院自身、無意識のうちに薄々感じとっていたのかもしれない。
(父さんが死んだのは、俺のせい……)
家を飛び出したまま、あてもなく走り続けていた劉院は、息を切らしてふいに立ち止まる。土砂降りの雨の中、ゆっくりと息を吸い込むと、少しだけ冷静になれた。
(そりゃ、嫌でも気を遣うよな……)
やたらと過保護な周りの大人たち、気を遣ってくる他人、全てに納得がいく。真実を隠すことに必死だったのだ。しかし、劉院にとって周りの大人たちが真実を隠してきたことはどうでも良かった。
彼にとって衝撃だったのは、何も知らない自分が誰よりも母を傷つけていたことだった。母は、一体今までどんな気持ちで──。
「バカだなあ、俺」
目じりが熱くなり、唇を噛み締める。泣くな。泣いちゃダメだ。今の己に、泣く資格はない。そうは思っても、我慢の限界だった。
今までの努力はなんだったのだろうか。母のために頑張ってきたというのに、母の心労は、突き刺さった棘は、劉院自身だったのだ。
「もう、嫌だ……疲れたよ……」
零れた本音により、全てが崩壊していく。頬をつたうものが、土砂降りの雨なのか、それとも涙なのかよく分からないまま、ずるずるとその場にしゃがみこむ。
「──劉院」
名前を呼ばれたのは、しゃがみこんでから数秒後のことだった。突然、頭上に降りそそぐ土砂降りの雨が止む。
驚いて顔を上げると、そこに立っていたのは思いがけない人物だった。
「い、おり……?」
「どうした?病み上がりなんだから、こんなにびしょ濡れじゃまずいだろ」
傘を持って劉院の前に立っていたのは、チームメイトである伊折だった。何故、彼がここにいるのだろうと思い、思わず周りを見渡す。その時はじめて、自分がツバメの巣の前にしゃがみこんでいるのだと気がついた。どうやら、無意識に通い慣れた道をたどっていたようだ。
「二人とも、はよこっちにおいで」
「風邪ひくぞ」
伊折の背後から更に二人、傘をさしてこちらにやってくるのが見える。先程別れたばかりのオーナーである隼人と伊折の兄である香折だ。
「たまたま、兄貴と隼人さんの家に寄っててさ。帰ろうとしてたとこなんだけど……傘もさしてないお前がいたからびっくりした」
「伊折……俺……」
「……ゆっくりでいいから、行こうぜ」
伊折の手が、差し出される。その手をとっていいのか、分からなかった。しかし、そんな劉院の手を伊折は掴んでぐいっと引っ張りあげる。よろけながら立ち上がると、伊折が少し困ったように笑った。
「悪いけど、今日は遠慮してやれない。でも、劉院が嫌なら俺たちは帰るよ」
今まであれで遠慮しているつもりだったのかと、普段の強引な姿を思い出しながら思考したが、それが伊折なりの優しさであることはとっくに知っていた。そうやって、時には強引に接しながらも、いつも劉院の気持ちを察して本当に嫌なところまでは踏み込んでこない。そして、どれだけ邪険に扱われようとも文句一つ言わない。そんな彼に、どれだけ救われていたのか、彼は知らないのだろう。
「チームメイトだろ。頼ってくれていいんだぜ。頼ってくれたら、俺はいつでもそれに応えるよ。どうする?」
決して無理やりではなく、あくまで選択を委ねてくるところが、彼を嫌いにはなれないひとつの理由だった。
「……これ以上、甘えてもいいのかよ」
「甘えられたことねえと思うんだけど」
「バカだなお前。俺はさ……──ずっとお前に甘えてたんだよ」
「……!」
伊折の驚いた顔を見て、先程まで顔を曇らせていた劉院が少しだけ笑った気がした。頬をつたっていた雨なのか涙なのか分からないそれを拭ってから、顔を上げる。
「伊折も来て」
「……分かった」
雨は依然として止む気配はないが、いつの間にか雷鳴は止んでいた。
