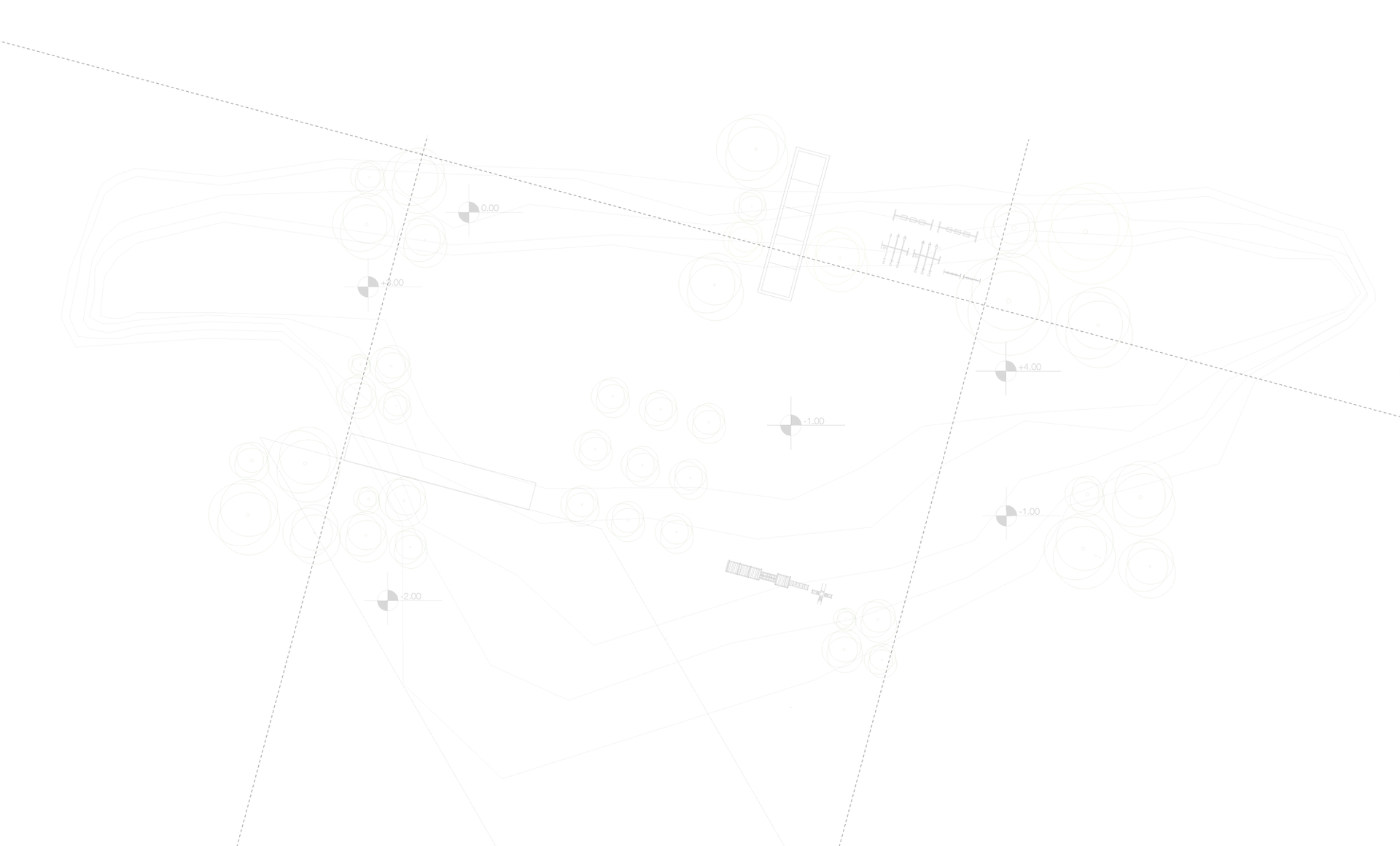
「雨、止めへんね」
客のいないガランとした店内で、暇そうに呟いたのは学院近くの商店街にある喫茶店「ツバメの巣」のオーナーである隼人だ。
彼の呟きに、そうですねと返事をしながら手持ち無沙汰だった劉院はテーブルを拭いていた。誰もいない以上、楽にしてて良いと言われてはいるが、数日バイトを休んでしまったため、せめてもの思いで店内の掃除に勤しんでいた。
隼人は、そんな彼を真面目な子だと感心しつつ、少々真面目すぎる性格であるが故にどこかで無理をしていないだろうかと以前から気にかけていた。体調を崩したと聞いた時はしっかり休養をとるように口酸っぱく念を押したほどだ。
本来ならもう少し休んでもらってもまったく問題はなく、それができるのであればそうしてほしいと強く思っている。──思っているのだが、彼がバイトに勤しむ理由を知っているが故に、あまり強く勧めることもできなかった。
「今日はもう店閉めよか。天気も最悪やし、なにより俺のやる気がのうなった」
「じゃあ、外のボード回収してきますね」
外では昼すぎから響き始めた雷鳴が未だに轟いていた。雨足も強く、確かにこれ以上は誰もやって来ないだろう。隼人の気分で早めに店を閉めることは時々起こりうるため、劉院は特に咎めることも無く閉店の準備へ取りかかる。
バイト歴が長いわけではないが、物覚えの良い劉院が手際よく閉店の作業を進めていくと、大した時間もかからず、あっという間に「CLOSE」のドアプレートがお店の入り口に掛けられた。
「いつも助かるわ。これ余り物やけど持って帰り」
「いいんですか?ありがとうございます」
「天気が悪いさかい気ぃつけてな」
「はい、お疲れ様でした」
客足が悪かったために余ってしまったらしいメニューの一部を受け取り、お礼を口にすると劉院は足早にツバメの巣を後にする。今日は叔父が家にやってくる予定になっていた。
実の妹である母に会うため、というのは口実で、恐らくいつものように実家に帰るよう説得したいのだろう。お見通しであるが故に、憂鬱だ。帰路につく足がとても重く感じられた。
水たまりだらけのアスファルトを踏みしめながら、今日はどうやって言い訳しようかなんて、悪あがきを思考する。しかし、これといって上手い案が思いつかないまま、あっという間に自宅へたどり着いてしまった。
「……まあ、いつも通りなんとかなるか」
適当に言い訳をしようと思案してから、覚悟を決めて鍵を差し込む。ゆっくりとそれを回せばカチャリと小さな音をたてて扉が開いた。玄関には既に見慣れた靴が綺麗に並んでいる。同時に、従姉の靴が一緒に並んでいることに気がつき思わずうわ、と小さな声を漏らした。
彼女の前から思わず逃げ出した先日のことが脳裏をよぎる。できることならば、今は彼女に会いたくなかったが、避けようのないことであることも分かっていた。
諦めて小さくただいまと口にしてから自分の靴を脱ぎ、綺麗に二人の靴の横に並べる。少しだけ強張る足でダイニングへ向かい、扉へ手を掛ける。
「──俺は、まだ討伐団に入団することを認めていないからな」
扉を開く前に耳にしたその言葉に、思わずドアノブを握っている拳から力が抜けた。次いで、それを宥める劉燐と、思い惑う母の声が聞こえる。今まさに、一番面倒な話をしているのだとすぐに理解ができた。むしろ、実家に帰って来いと説得されるよりも面倒な話だ。
「まあまあ、父さん、その話はもういいじゃん」
「いいわけないだろう」
「……あの子が決めたことだもの。兄さんも分かってあげて」
「バカを言うな。もし、劉院まで魔物に殺されるようなことがあったらどうする?あの子の父のように?」
叔父が討伐団に入団することを反対していることは百も承知だった。劉院の父は、魔物に殺されたからだ。
父のことを実の弟のように可愛がっていた叔父は、同じように劉院のことも可愛がっていた。だからこそ、劉院が同じ道をたどるのでは無いかと、心配しているのだ。その心配が、彼を焦らせているとも知らずに。
「そうならないための養成学院だよ。それに、私だってそのために入学したんだ。死なせないよ」
「──え?」
劉燐の思いがけない言葉に、息を飲む。そんな話は、一度たりとも聞いたことがなかったからだ。
(あいつが、入学してきたのは俺のため……?)
劉院の入団希望を反対している叔父が何故、彼女の学院への入学を認めたのだろうかと不思議に思っていた。そもそも、彼女が学院への入学を決めた理由さえ、劉院には分からなかった。
ただ、彼女は昔から自由気ままな人だったから、いつもどおりの気まぐれで学院に興味が湧いたのだろうと深く考えることはしなかった。そのうえ、彼女は口が上手い。適当に叔父を言いくるめて入学することは簡単だ。だからこそ、彼女の真意が自分のためだったなんて、青天の霹靂だ。
(なんだよ、それ……)
ショックだった。それほどまで、叔父家族が自分のことを心配しているのだと言えば、聞こえはいいだろう。しかし、それは彼にとって、自分自身の弱さを突きつけられただけだ。
大人たちにとって、劉院はいつまでも誰かに守ってもらうべき存在なのだ。そして、それを少ししか歳の変わらない彼女に任せたことが、より深く劉院の心を傷つける。
(分かんねえよ……たった四歳しか変わらないのに、どうしてあいつは良くて、俺はダメなんだ)
彼女と自分の何が違うのか、何も理解できなかった。彼女自身、心はまだこどものままだと言っていた。しかし、大人たちからは自立したひとりの大人として認められている。
どうして、ともう一度、混乱した頭が思考する。そして、彼が彼女を大人にしてしまったのだと気が付き、愕然とした。入学を決めた当時、本当は彼女もまだこどものままでいたかったのかもしれない。
「劉燐ちゃん。いつも劉院を気にかけてくれてありがとう」
「いいのよ。あたしが好きでやってることだもの」
ドアノブに掛けていた手はいつの間にか宙をさまよっていた。いつもどおりの自分を保ったまま、この部屋に足を踏み入れることなどできるはずがない。
幸い、バイトが予定よりも早く終わったため、本来の帰宅時刻までまだ時間がある。故に、彼等も油断しているのだろう。でなければ、先程のような会話を無防備に晒したりはしない。
一度家を出て、頭を冷やしてこよう。いつも通りの帰宅時間に何も知らない顔をして帰るべきだ。そう判断して、踵を返す。
更なる衝撃が劉院を襲ったのはその時だった。母と劉燐の会話を遮るように、叔父の呟きが、劉院の耳に鮮明に響いたのだ。
「あの子の父親は、あの子を守って死んだんだ」
突然、頭を鈍器で殴られたかのような感覚に襲われた。同時に、酷く息が詰まる。
「もしかしたら、劉院が同じように誰かのために犠牲になることもあるかもしれないと考えるだけで……」
「──嘘だ。そんな……!」
これ以上は耐えられなくて、劉院は家を飛び出した。土砂降りの雨の中、傘を持つ暇もなく。
「……劉院?」
玄関の扉の閉まる音に、三人ははっと顔をあげる。劉院が帰ってきたのだと思い、慌ててその口を閉じたが、いつまで経っても彼が姿を現すことはなかった。帰宅したのではなく、家を飛び出したのだから当たり前だ。玄関に置き去りにされた紙袋に気がついた時には、既に彼の姿はどこにも見当たらなかった。
