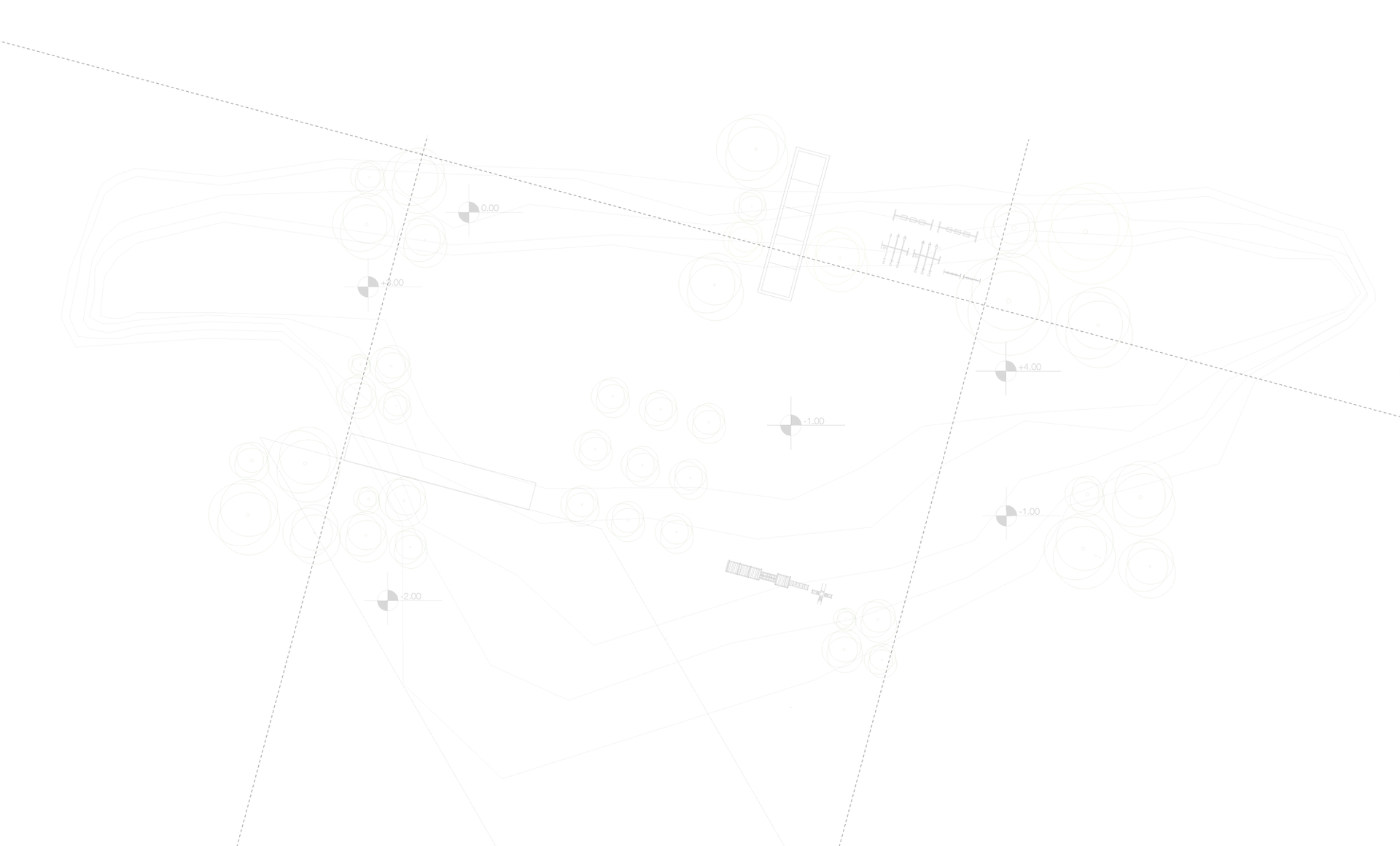
空一面を覆う灰色の雲が一瞬、ピカリと光るのが目に入る。それと同時に、握りしめていた模造の長柄棒が弾かれた。カランと音をたてて地面に転がるただの棒を横目に、振り払われた相手の握る同じ物をギリギリで避けてから、最後のあがきとして足を払い除けた。
「あぶね」
そうこぼしながらも、軽々とかわすものだから苛立ちを覚える。足を払い除けた反動で、そのまま地面に倒れ込むと、こつんと頭を叩かれた。
今にも降り出しそうな曇天を背景に伊折のニヤリと笑った顔が目に入る。
「はい、俺の勝ち」
「……っ」
「伊折!劉院!降り出しそうだから戻ってきなさい」
悔しくて、勝ち誇った顔をする伊折を無言で睨みつけていると、林檎の声が梅雨の重い空気に反響する。既に屋内に避難したらしい林檎と姫が手を振っていた。
もう一度空が光ったかと思うと、遠くで雷鳴が響き渡る。直後、ぽつぽつと冷たい雨が頬を濡らしはじめた。
「あーあ、降ってきた。劉院、戻るぞ」
「……ああ」
地面に転がっていた身体を起こし、伊折から差し出された手をチラリと確認してから、それを無視して立ち上がる。
体調を崩してから、やたらと周囲の人間からの善意が劉院を苛立たせる。優しくされればされるほど、まだまだこどもなのだと実感させられるようだった。それが悔しくて、つい伊折にいつも以上に冷たく接してしまう。そんな自分がいっそう腹立たしかった。
「ちょっと劉院」
「なんだよ」
伊折を置いて先に屋内に戻った劉院を林檎が呼び止める。さすがに今のはあからさますぎた自覚がある。文句を言われるのだろう。
そう思っていたのに、突然目の前に何かが飛んできた。
うわ、とたじろぐと同時に、やや乱暴にガシガシと頬を擦られる。林檎が手にしていたタオルで拭かれているのだとすぐに気が付くと、思わずその手を払いのける。
「やめろよ」
こどもじゃないんだから、と言いかけてその言葉をぐっと飲みこむ。
「なに?文句ある?病み上がりなんだから、ちゃんと拭いときなさいよ」
「そういう気遣い、マジでいらねえ」
林檎の優しさが、更に劉院を傷つける。同時に、素直に優しさを受け止められない自分に失望した。いっそのこと、自分のことなんか嫌いになってくれればいいとさえ思う。
「あんたバカ?」
「いって」
いつものように、怒って、文句を言って、もう知らない、と突き放してくれると思っていた。そうしてくれたのならば、どれだけ良かっただろうか。
しかし、彼女はまったく怒った素振りを見せず、劉院の額を指で弾くだけで呆れたように笑っていた。
「私があんたのことを気遣うわけないでしょ」
「……それは」
そうだけど、と口ごもりながら指で弾かれた額をさする。
「これは気遣いじゃなくて、ただのお節介」
「違いが分からん」
思わずそう口にする。すると、林檎は「そうでしょうね」と言ってもう一度呆れたようにはにかんだ。
「あーあ、どいつもこいつも」
「なんなんだよ」
「チームメイトなんだから、お節介くらい焼くわよ。あんたも、もう少し頼ってくれていいのよ」
「……」
「林檎、俺には?」
「あんたは自分で拭きなさい」
頭に疑問符を浮かべていると、いつの間にか屋内に避難していた伊折が劉院の背後から声をかける。林檎がタオルを伊折に投げつければ、やれやれといった様子で彼はそれを受け取った。
「姫、この扱いの差どう思う?」
「え、えっと……三人とも仲良しだなって思います」
二年と少し前、学院の制度によってこのチームを強制的に組まされた当時からよく分からない奴らだと思っていた。しかし、余計に何も分からなくなってしまった。
林檎がただのお節介だと主張するのも、冷たくあしらった伊折がいつまでもへらへら笑っているのも、先程の一連のやり取りを見て仲良しだと言う姫のことも、何も理解ができなかった。
同時に、いつまでも苛立っている自分が馬鹿らしく思えた。この先もずっと、この三人は変わらないのだろう。焦って大人になりたがっている自分だけが、やけにちっぽけだ。
「……伊折、ごめん」
「え、急になに……?」
「なんでもねえよバカ」
雨はまだまだ降り止まないが、少しだけ気持ちが軽くなった気がした。何も分からないこの三人との学院生活はこれからも変わらず続くのだろう。
