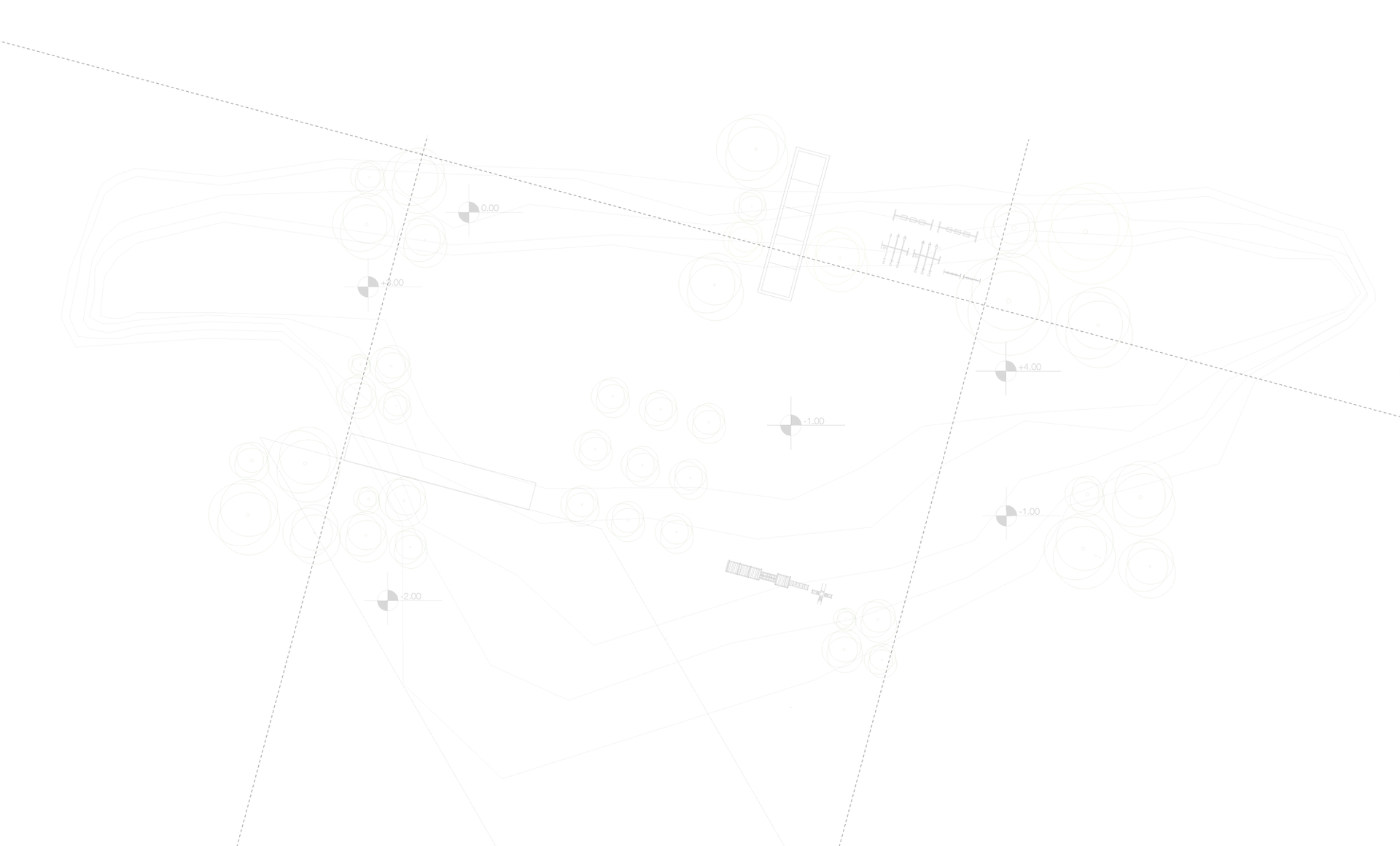
劉院が学院に復帰したのは体調を崩してから二日後のことだった。思っていたよりも拗らせてしまい、母にも心配をかけてしまった。今後は気をつけなければと考えながら、学院の門をくぐる。
本日の時間割を思い浮かべながら、ふと親友から借りっぱなしのノートの存在に気がついた。幸い、休んでいる間に該当の授業はなかったため、問題はないだろうが早めに返しておこう。そう思い、急ぎ足で教室へと向かう。
しかし、そんな劉院を呼び止める少し高めの凛とした声を耳にし、ふと足を止めた。
「おはよう。もう体調はいいのかい?」
「やあ、劉院。元気になったようでなによりだ」
「劉燐……と、良太さん。おはようございます」
声の聞こえた方へと視線を向けると、昨年の春から同じ学び舎に通うことになった従姉が手を振っている。隣には彼女のチームメイトである宝前良太の姿もあった。軽く会釈をすれば、彼は笑顔でそれに応える。
知る人ぞ知る有名な商人の一人息子である彼の笑顔は親しみやすく、気兼ねない印象を与えつつも気品に溢れていた。そんな彼と言葉を交わすのは、失礼がないだろうかと少し緊張してしまい、思わず身が引き締まる。
すると、そんな様子を察したのか、良太は劉燐の肩をポンと叩くと先に行っているよとだけ言い残し、その場を離れた。気を遣わせてしまったようでなんだか申し訳ない気持ちになり、思わず表情を曇らせる。そんな劉院のことを面白い物を見たというようにケラケラと劉燐が笑った。
「あはは、そんなに緊張する必要ないのに。むしろ、良太のことを遠巻きにするのはあんたくらいだ」
「遠巻きになんかしてねえよ。ただ、俺とは住む世界が違うから、失礼がないかと余計なこと考えちまうだけだ」
「そんなことないよ。私達の住む世界はいつだって同じだ。確かにお互いの環境はまったく違うから、見える景色は別物なんだろうけど。それはさておき」
そんなよく分からない会話を交わしてから、劉燐はじっと劉院の顔色をうかがった。熱は下がったと聞くが、まだ本調子ではないのだろう。少しだけ気だるげそうな彼の様子に、彼女が表情を曇らせる番だった。
「……あんたが倒れたって聞いて、ちょっと……いや、かなり心配した」
「大袈裟だな。ちょっと体調を崩しただけだろ?もう大丈夫だから」
「でも、まだ本調子じゃないんでしょ?無理しちゃダメだからね。……ねえ、劉院。やっぱり実家に帰ってきなよ。私たちはいつでも歓迎するんだよ」
「……何度も言ってるけど、実家には帰らねえ。もうこどもじゃねえんだから、心配いらねえよ」
実家には劉燐とその両親、祖母が住んでいる。学院に入学する三年前までは、劉院も母と一緒にそこで暮らしていた。
学院に入学するのを機に、実家を出たいと申し出たのは劉院からだった。いつまでも世話になり続けるのが申し訳ないという気持ちと、時々やってくる親戚たちに気遣われ続けることに嫌気がさしたからだ。当たり前のように反対されたが、あの頃はまだ中学生だったのだから仕方のないことだ。
それでも今後のために、となんとか祖母と叔父を説得したのを今でも覚えている。その日からずっと、まだこどもなのだからと諭され続けているのは今でも変わらない。
「こどもだよ。まだ高校生になったばかりなんだよ」
「分かってる」
「分かってない。私だって成人を迎えたからってすぐ大人になれるわけじゃないのよ。まだまだ気持ちはこどものまま。だから劉院、君はそんなに焦って大人になろうとする必要なんてないの」
「……」
言いたいことはよく分かっていた。世間一般的に己はまだまだこどもで、大人に頼らないと生きていけない。でも、大人とこどもの違いってなんだろう。気持ちはまだまだこどもだと言うのならば、一体いつ大人になれるのだろうか。
叔父も叔母も、自分を本当の家族のように思ってくれているのは分かっている。しかし、劉院にとっては気遣われることがなによりの苦痛だった。
見返りを求められているわけではないと頭では分かっていても、返せるものが何もないから素直に受け取めることができない。なにより、無償の愛に縋り続けてしまったら、いつまでも変われない気がする。
「悪いけど、友達にノート返さなきゃだから……じゃあな」
「あ、待ちなさい!……もう!」
なにも言い返すことができなくて、足早にその場から逃げ去ることを選んでしまった。
劉燐とその家族が純粋に心配してくれているのは嫌というほど伝わっていた。感謝だってしている。
感謝しているからこそ、早く討伐団に入団して、お世話になった人達に恩返しがしたかった。母との生活も今より楽になるはずだ。ただ、それだけのことなのに。
「……なんで誰も分かってくれねえんだよ」
「あ、劉院。おはよう。今日は登校できたんだな……劉院?どうした?」
一時間目の学年別授業が行われる教室に滑り込んでから、小さな本音がぽろりと漏れた。劉院が登校していることに気が付いた親友が、いつまでも入口に立ち尽くしている彼を案じて歩み寄る。
「航琉。俺、間違ってるのかな」
「……俺は、劉院のしたいこと応援してるよ」
「……うん」
本当は、とっくに分かっていたんだ。自分のわがままで、たくさんの迷惑をかけていることも、これが正解じゃないということも。
