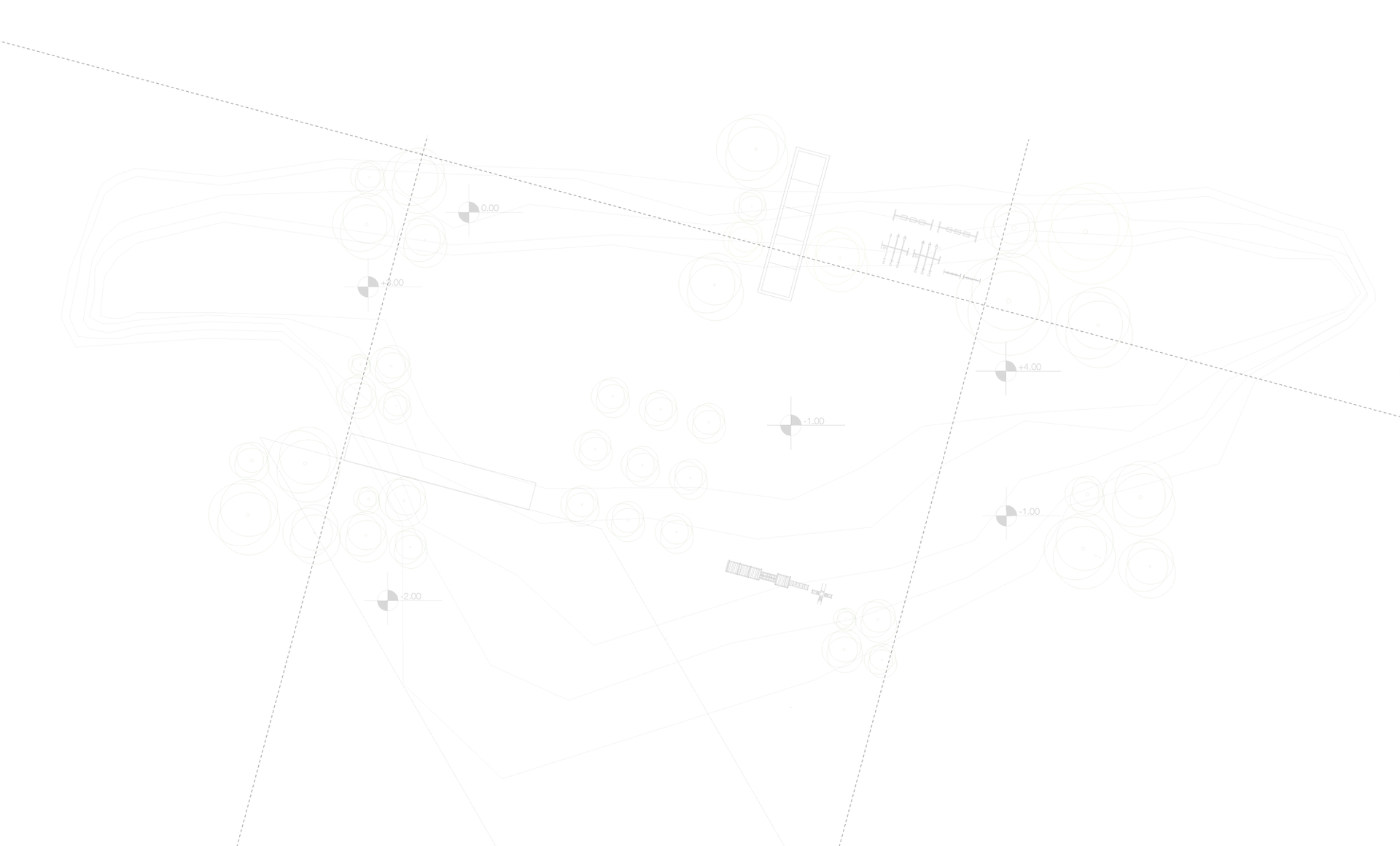
お腹を空かせた生徒達で賑わう食堂の窓際最奥にある四人用のテーブルに花鈴とリョクが対面する形で座っていた。
久しぶりに一緒に食事でも、と誘ったのはリョクの方からで、もうひとりの旧友が到着するのを待ちながらぽつぽつと言葉を交わす。こうして揃って食事をとるのはいつぶりだろうか。自然と会話が弾み、最近のチームのことだとか、今は懐かしい一緒にチームを組んでいた時のことだとか、そういった他愛もない話に花を咲かせた。
「悪い、遅くなった」
「ああ、やっと来たね」
各々で注文した食事を半分程食べ進めた頃、ようやく最後の一人が到着する。二番目の兄が毎日作ってくれるというお弁当をテーブルに置き、リョクの隣に腰掛けると、彼は早々に大きなため息をついた。
「おや、しめっぽいねえ」
「幸せが逃げますよ、伊折」
「ちょっとは俺に優しくしてくれ……聞いてくれよ。さっき林檎にまたすげえ文句言われてさ」
お弁当箱を慣れた手つきで広げ、お行儀よく手を合わせる。兄お手製の卵焼きを口に運びつつ、大きなため息の原因を語れば旧友達は微笑ましくそれに耳を傾けた。
「林檎さんは真面目ですからね。彼女にとっては大切ななことだったのでしょう」
「そんなに怒らなくても良くね?」
「まあ、あんたは時々適当だからねえ。そういうところが香折先輩に似てる」
「やめてくれ」
伊折にとっては一番言われたくない言葉だ。無論、分かって言っているであろうことは明確だが、本気で言ってるわけではないことも分かっていた。旧友とのただのじゃれ合いである。そんな、少しだけ懐かしいあの頃と変わらない昼休み。
「そういえば、劉院くんはその後体調はどうですか?」
「あ、そう!それ!これどう思う!?」
他愛もない会話のなかから、先日高熱を出し早退した劉院の話題があがる。その途端、伊折が自身の携帯端末を机の上に置いて画面を指さした。
そこに表示されていたのは誰もが知る学院用の連絡用チャットアプリだ。伊折から送信された熱は下がったか、皆心配してたぞ、困ったことがあればいつでも言えよ、といった労りのトークのあと劉院からの返事はというと──
『心配いらねえ』
たった一言、これだけである。
「冷たくねえ!?」
せっかく心配してやってんのに、と伊折は口を尖らせる。医務室にいた劉院は、伊折が想像していたよりも弱っていた。でなければ、あんなに素直に礼を言うはずがない。だからこそ、いつも以上に心配になり、普段は滅多に送らないチャットアプリまで利用したというのに、あっという間にいつもと変わらない劉院に戻ってしまったようだ。
「いつも通りの返事ができるってことは心配いらないんじゃないかい?」
「そうですね。劉院くんらしいと思いますよ」
「それはそうなんだけど。はあ……俺、やっぱリーダー向いてねえのかな。チームメイトと仲良くなるコツとかあったら教えてくれよ」
二度目のため息をつきながら、食べ終えたお弁当箱を綺麗に片付ける。伊折にしては珍しく落ち込んでいるようだ。そんな彼の様子に、リョクと花鈴は顔を見合わせた。
二人の知っている伊折は、人懐っこくいつでも元気がある、少し甘えたな弟のような存在だった。実際、家では三男の末っ子なのだから、何も間違ってはいない。しかし、新しいチームを組んでからは、リーダーという立場上からなんだか大人びたように思っていた。そんな伊折に、寂しさを感じていたのだが根っこは何も変わっていないようで少しだけ嬉しい気持ちが溢れる。
「あんたが変わっていなくてちょっと安心したよ」
「ふふ、そうですね」
「なんの話?」
「こっちの話」
二人が揃って嬉しそうに笑うので、伊折は更に苦虫を噛み潰したような表情を浮かべる。真剣なんだけど、と真面目な姿勢を見せると、そうですねえとリョクが少し考える素振りを見せた。しかし、伊折が欲しい言葉を与えてやれるとは思えず、すぐに考えるのをやめた。代わりに、素直な気持ちを言葉につづる。
「伊折はよくやっていますよ。そもそも、僕らの中で一番人付き合いが上手いのは伊折じゃないですか。たまたま、少し素直になれない子達が集まってしまっただけですよ」
「そうそう。一年目のことを考えたらここまで打ち解けられたのはあんただからこそだよ。アドバイスすることなんて何もないね」
「そうは言ってもさ、俺としてはもう少し頼ってほしいっていうか」
「リーダーなんて所詮ただの飾りだよ。気負いすぎなんじゃない?」
花鈴の言うことはごもっともである。
リーダーというのは所詮、組織の仕組み上いた方が都合が良いだけの役職で、チームをまとめることが使命ではない。
伊折自身も、チームメイトを率先してまとめたいわけではないのだ。ただ、少しでもチームメイトの力になりたい。それだけの気持ちなのだが──
「余計なおせっかいかな」
「君はそれでいいんですよ」
「ホントかよ……」
未だに自信が無いと不安げな顔を見せているが、他人から見ればオベイは十分にチームとして上手くいっている。素直になれない林檎も劉院も、伊折の何気ない気遣いには気づいているのだが、それを知らないのは彼だけだ。
「伊折、不安になることもあるでしょう。でも、今の僕達なら大丈夫ですよ。自分の思ったように、やってみたらいいと思います」
「そうそう。何も心配いらないよ」
旧友二人に改めて太鼓判を押されてしまえば、これ以上は落ち込んでいられない。昼休みの終了を告げる鐘の音を聞きながら、よしと顔を上げた。それは、二人が昔からよく知る伊折の姿だった。
