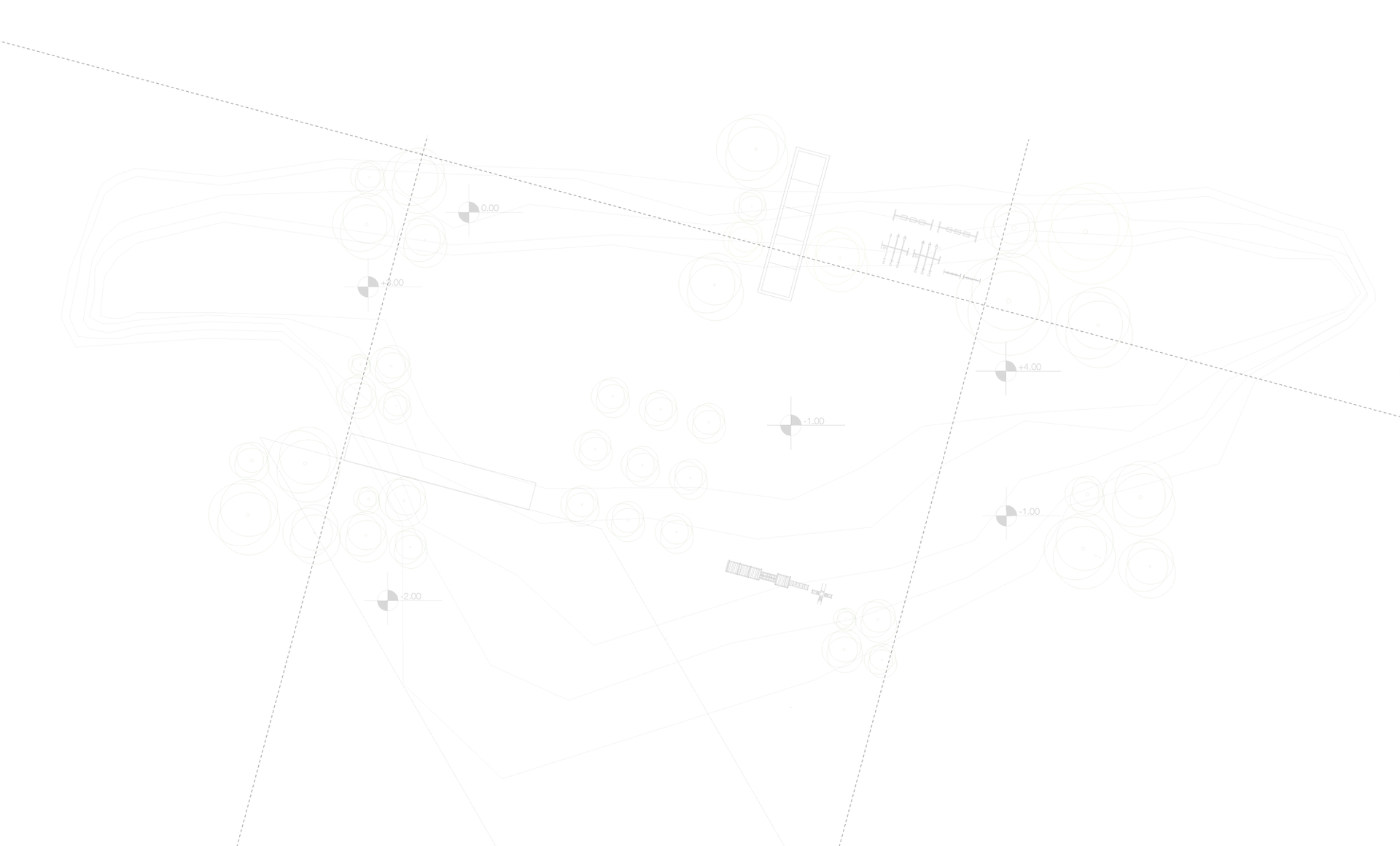
きぃ、きぃと、さびたブランコが鈍い音をたてる。
周囲はたくさんの人で溢れかえっているというのに、さびた鉄の擦れる音だけがやけに耳に響いた。まるで、世界にひとりぼっちになってしまったかのような感覚だ。
(俺、どうしてここにいるんだっけ)
周りを見渡せば、仲慎ましげな親子が楽しそうに遊具で遊んでいる。しかし、少年はひとりぼっちだった。いや、誰かと一緒にここを訪れたような気がする。何故なら、彼はまだ小さなこどもなのだから。
「劉院」
「わっ」
聞きなれた声で彼の名を呼びながら、大きな手が背中を押した。少年の身体がブランコごと大きく空を舞う。今なら雲ひとつない青空に手が届きそうだ。
「そろそろ帰ろう」
そう言って、重力に従い地面へと落ちてきたブランコに乗る劉院の身体を受け止める。顔を上げると、そこにはあの日から何ひとつ変わらない父の優しい笑顔があった。
「うん」
差し出された手を握り、公園の出入り口へ向かって父と二人で歩きながら劉院は周辺をぐるりと見渡した。親子に人気の森林公園なだけあって、劉院と同じくらいのこども達が両親に囲まれて楽しそうに笑っていた。
母さんは、どうして一緒にいないんだっけ。
そう思ったが、すぐに思い出した。母は体調を崩しやすく、いつも父に遊んでもらっていた。寂しい気持ちもあったが、母の調子がいい日に時々家族揃って遊びに行けるだけでも充分だった。
「劉院、おかえり」
「母さん?」
公園の入り口に、家で留守番をしているはずの母が立っていた。顔色が悪いのはいつも通りだが、調子がいいのかにこにこしながら手を振っている。こどもながらに嬉しくなって、母の元へと駆け寄る。父の手を離して。
「母さん、寝てなくていいの?」
「気分が良くなったから迎えに来たの。一緒に帰ろう」
「うん!あ、父さん――」
母の手を握って、もう片方の手を父に差し出した。しかし、そこに父の姿はなかった。
あれ、と慌てて周囲を見渡すが、どこにも父の姿が見当たらない。途端に、なんとも言えない不安がこみあげてきた。
──劉院
ふと、劉院の不安を振り払うかのように父でも母でもない、誰かが名を呼ぶ声が聞こえた、聞いたことのある声だ。誰の声だっけ、と思考しながら母の顔を見上げる。先程までの笑顔は消えていた。ただ、悲しそうに、首をふっている。
「母さん、どうしたの」
「なんでもないよ」
「でも」
──劉院。おーい、劉院!
父がいなくなった公園の入り口に再び視線を向けると、先程よりも強く名を呼ぶ声がこだまする。母でもない、父でもない、この声は──
「劉院!」
「っ!」
突然、意識が覚醒する。肩を揺さぶられて初めて、自分が居眠りをしていたことに気がついた。同時に、自分の名を呼んでいたのは親友であることを思い出す。
「授業終わったぞ?」
「え、うわ、マジか……」
いつから居眠りをしていたのだろうか。真っ白なままのノートを見下ろし、やってしまったとこうべを垂れる。最近はバイトの数を増やしていたから疲れが出たのだろうか。重く、深く、息を吐く。それと同時に、ほらと航琉のノートが差し出された。見た目こそ綺麗だが、芸術的な落書きが施されているであろう親友のノートだ。
「俺のノート見せてやるから」
「サンキュ。すぐ返す」
「急がなくていい。それより、お前顔が赤いぞ」
「え」
「熱があるんじゃないか?」
そう言われた途端、突然身体が重く感じられる。不調というのは、自覚した途端に悪化するのは何故なのか。これは、確かにまずいかもしれない。
しかし、どうせあと一時間で今日の授業は終わる。どうするべきかと思考を重ねたが、その思考さえも頭が重くて上手く回らない。
「……医務室行ってくる」
「ついてく?」
「いい。先生に伝えといてくれ」
「分かった。無理すんなよ」
「ん、助かる。ノート、次の授業までに返すから」
ノートを受け取って酷く重い腰をあげる。教室を出ると、じめじめした空気が頬を撫でた。どんよりとした窓の外の景色が鮮明に映る。六月に入り、本格的な梅雨がやってきた。今にも降り出しそうな曇り空と湿度の高い空気が、劉院の身体に重くのしかかる。
「あ? なに? 体調が悪い? それくらい自力でどうにかしろ!」
医務室に到着するや否や発せられた理不尽すぎる言葉に、あと一時間の授業なんて直接サボってしまえば良かったと心の底から後悔した。この養護教諭、アルバート・アッカーソンは男の扱いが雑だということをすっかり失念していた。
「……と、言いたいところだが。さすがにヤバそうだな。熱計って帰れ」
「あ、はい」
後悔した矢先、案外まともな対応が返ってきて拍子抜けする。というよりも、それ程他人から見て明らかに顔色が悪いらしい。投げられた体温計を受け取り、座れと促されたパイプ椅子に腰掛ける。熱を測りながら、ぼんやりと家に帰ってからのことを考えていた。
(家帰ったら、母さんの夕飯だけ適当に準備して……あ、洗濯物干してねえ。体調がマシになったらまとめてやればいいか。買い物は最悪、劉燐に頼むしかねえな)
ぐるぐると思考していると、ピピと体温計が熱を測り終えたことを知らせる。恐る恐る覗き込むと、そこには想像していたよりも高い数値が表示されていて、思わずうわ、と小さな声が漏れる。
「八度二分……これはダメだな。親御さんに連絡してやるから迎えに──」
「いらない!」
「あ?」
しまった。そう思った時には、既に遅い。
病人とは思えないほどの大きな声が、医務室に響きわたる。とたんに、アルバートの表情が強ばった。
「大丈夫です。ひとりで帰れます」
「いや、微熱ならともかく高熱出してる生徒をひとりで帰らせるわけには行かねえから。……親御さん仕事忙しいのか?」
「いや、その……」
「……」
どうしたものかと、言葉がつかえる。劉院の唯一の家族である母は昔から身体が弱く、小さい頃に父がいなくなってからもそれは変わらない。むしろ、悪化している。
母なりに元気な姿を見せようと頑張っていることは知っていた。だからこそ余計な心配をかけたくないし、自分のことを第一に考えてほしい。いくらでも支えてやれる。そう、思っていた。
ところが、無理をしすぎだ結果がこれだ。帰宅すればば体調を崩したことはすぐにばれてしまうが、不要な外出を母にさせたくないのが本音だった。
「仕方ねえな。あと一時間ベッドで寝てろ。授業終わったら適当な先生に声かけて送ってもらうから。いいな?」
「……すみません」
いつまでも黙っていると、先に痺れを切らしたアルバートにベッドへと放り投げられた。扱いは雑だが、意外にもしっかりと養護教諭らしい仕事をしていて少し驚く。ベッドに横になると、途端に眠気が襲ってきた。
──ああ、少し疲れた。でも、少し休めばすぐ元気になる。また、明日からも母さんを支えてやれる。大丈夫。何も心配いらねえから……。
自分に言い聞かせながら、瞼を閉じる。いつものようにあの日から変わらない父の面影が、肩を支えてくれていた。その姿は、少しずつ曖昧なものになっていく。
